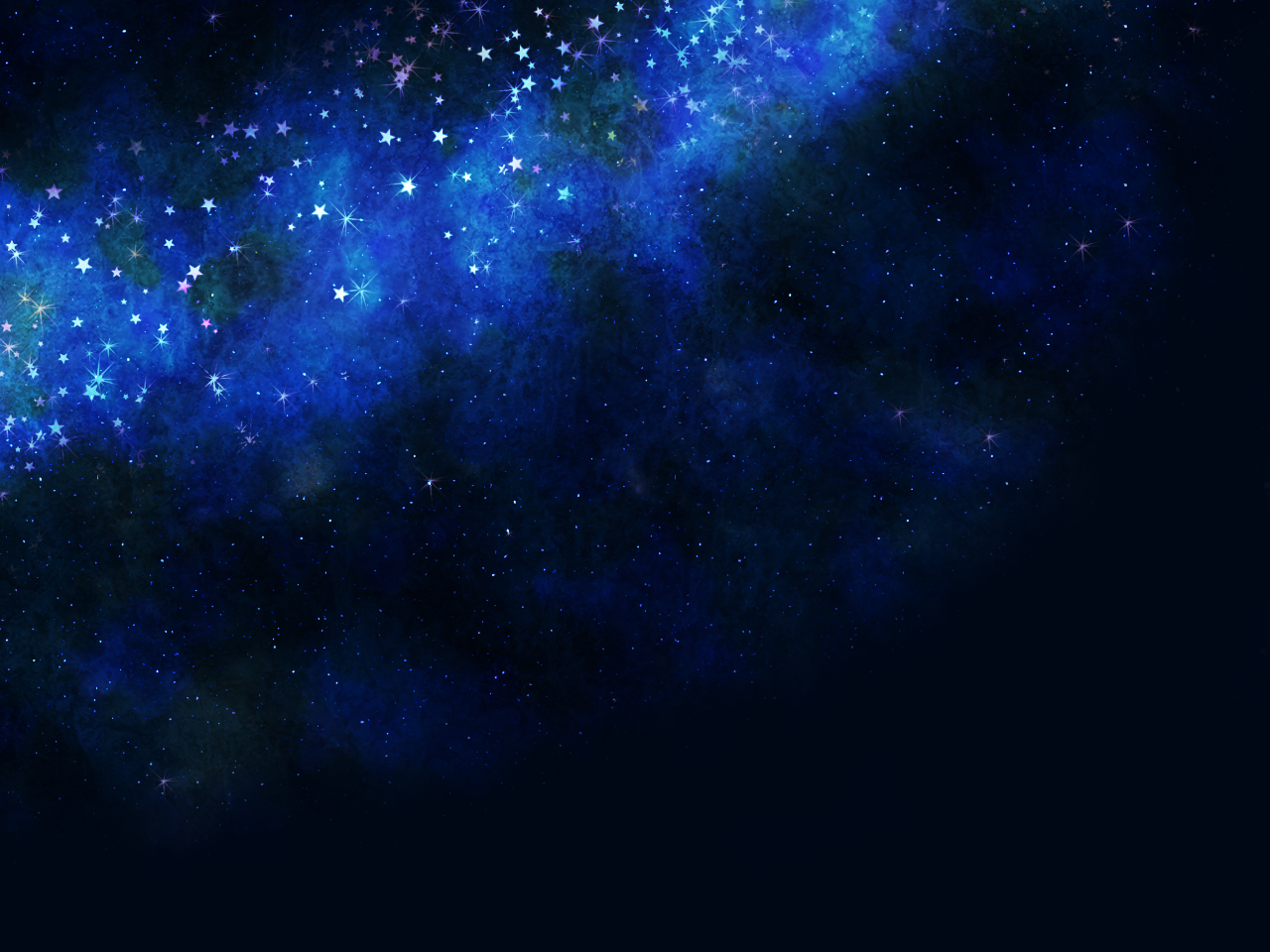笑顔一つ足りないだけで、どうしてこんなにも暗くなるのだろう。あの事件から、音也無しでのツアー準備が始まった。それは翔が強く望んだことで、音也が目を覚ました時に中止になっていたら彼は酷く悲しむだろうと全員が承諾してくれたことだった。それなのに、六人に戻ったST☆RISHが以前のようなハーモニーを奏でることはなかった。
「だから、そこのステップは違うでしょう! 音也がそこに入るんですよ、もう一歩先に踏み込まないと!」
「すまない……」
「トキヤ、もうこのフレーズ何回目ですか……全然先に進んでません……」
「イッチー、少し休憩を挟まないかい? 全員、集中力が切れてきているよ」
「ですが、これでは全然初日に間に合いませんよ!」
明らかに焦りを見せるトキヤをなだめるように、レンはドリンクボトルを手渡した。同じことを繰り返し続けたセシルも、疲れ以上に飽きが見え、場の少し重い空気に那月も眉を下げてしまう。場を和ませてくれそうな春歌は、ツアーで発表される新曲の方で手いっぱいの状況だった。
「俺まだ余裕あるし、別の曲のステップ確認するわ」
「翔ちゃん元気ですね」
「おう! ま、俺様にとっちゃこんなもん朝飯前だぜ!」
「あれ、その曲……」
翔が開いたCDケースに、レンは首を傾げた。
「イッキとの、デュエットじゃ」
「……約束、したからさ。二人でカッケー詞入れて、ツアーで歌うって。アイツはぜってー目を覚ます。だから、この曲は、この曲だけは完璧にしないといけねえんだ」
仮に音也がツアーまでに目を覚ましても、間に合わないとでも言いたいのだろう。だがレンは口には出さず、寂しげに微笑んで何も言わなかった。音也が目を覚まして、二人で歌詞を入れて、ステップを合わせて、練習をして、そんな時間が十分にあるとは言えない。だが、翔は視線を横に移し、頷いた。
音也はここに居る。彼がゆっくり頷き返したのを確認し、翔はCDプレイヤーの再生ボタンを押した。
はっきりとした気配は感じられないが、それでも互いの距離感を目で確認してステップを合わせる。少しでも、時間が惜しかった。
「翔ちゃん……」
「サビのここ、どうすっか」
「タンブリングダイスってどういう意味だっけ」
「『ダイスを転がせ』」
「俺と翔の歌でしょー、うーん……」
その日の練習も終わり深夜にさしかかる頃、翔は寮の外のテーブルに懐中電灯を転がし楽譜を睨んでいた。手元のペンでテーブルを叩き、リズムに合わせてそれまで書き連ねた詞を口ずさむ。横に居る音也はそれを聞きながらその横顔に小さく溜息を吐いた。
「……ねえ、翔。今日はもうやめない?」
「はあ? 何言ってんだよ、時間が足りないって分かってんだろ?」
「うん。だから、もう俺のことは飛ばして、それで六人で出来るようにしようって、翔から皆に言ってよ」
リズムを刻んでいたペンが、翔の手から落ちる。咄嗟に手を差し出した音也をすり抜け、ペンは呆気なく地面へ落ちた。
「あー、もう。翔自分で拾ってよ?」
ペンを追っていた音也の視線が、すいと上げる。
「翔?」
音也が問いかけても、翔は視線を返すこともない。
「なんだよ、それ」
「え?」
「なんでだよ! 皆お前のこと待って、それで頑張ろうって!」
「……だって、このままじゃ」
「俺たち七人でST☆RISHだろ! お前が居なきゃ、意味ねえじゃん!」
「このままじゃ全然進まないよ! 俺のこと待ってないで、六人でツアー行ってよ!」
「なんでお前が、」
「だってこのままじゃ、」
「諦めてんだよ!」
「皆がバラバラになっちゃう!」
ボツ、と滴が譜面に落ちて書きこまれた歌詞が滲む。
ダメなんだ、音也が居ないと。約束をしていた。初めてのツアーで、二人で歌うと。七人揃って、喜びも感謝も全部込めて日本中に届けようと。
約束をしていたのに。
「皆、無理してる。俺分かるんだ、皆が無理して練習してるの。俺抜きでやれば、もっと皆楽にできると思う。このままじゃ、誰かがいきなり倒れちゃうかもしれない」
「そんなの、」
「ない、なんて言える? 翔だってこんな夜中まで頑張ってて……このまま続けて、ファンの皆の前で全力を出せる?」
音也の言葉は、間違ってはいない。あんなにピリピリした練習を続けていたら確実に誰かがダメになる。自分の体力だって、分からないわけではない。でも今は、無理をしないといけない時だと思っていた。無理をしてでも、成さねばならないと。
それなのに、彼の為と頑張っていたのに。
「お前が、それを言うなよ」
当の本人が、それを否定する。
「俺が言わなきゃ、ダメなんだよ」
翔は譜面をかき集め、音也に目もくれず立ち上がった。
「なんだよ、それ」
ここ数日泣いてばかりだと、自分でも思う。
いつの間にか音也の気配はなくなっていた。