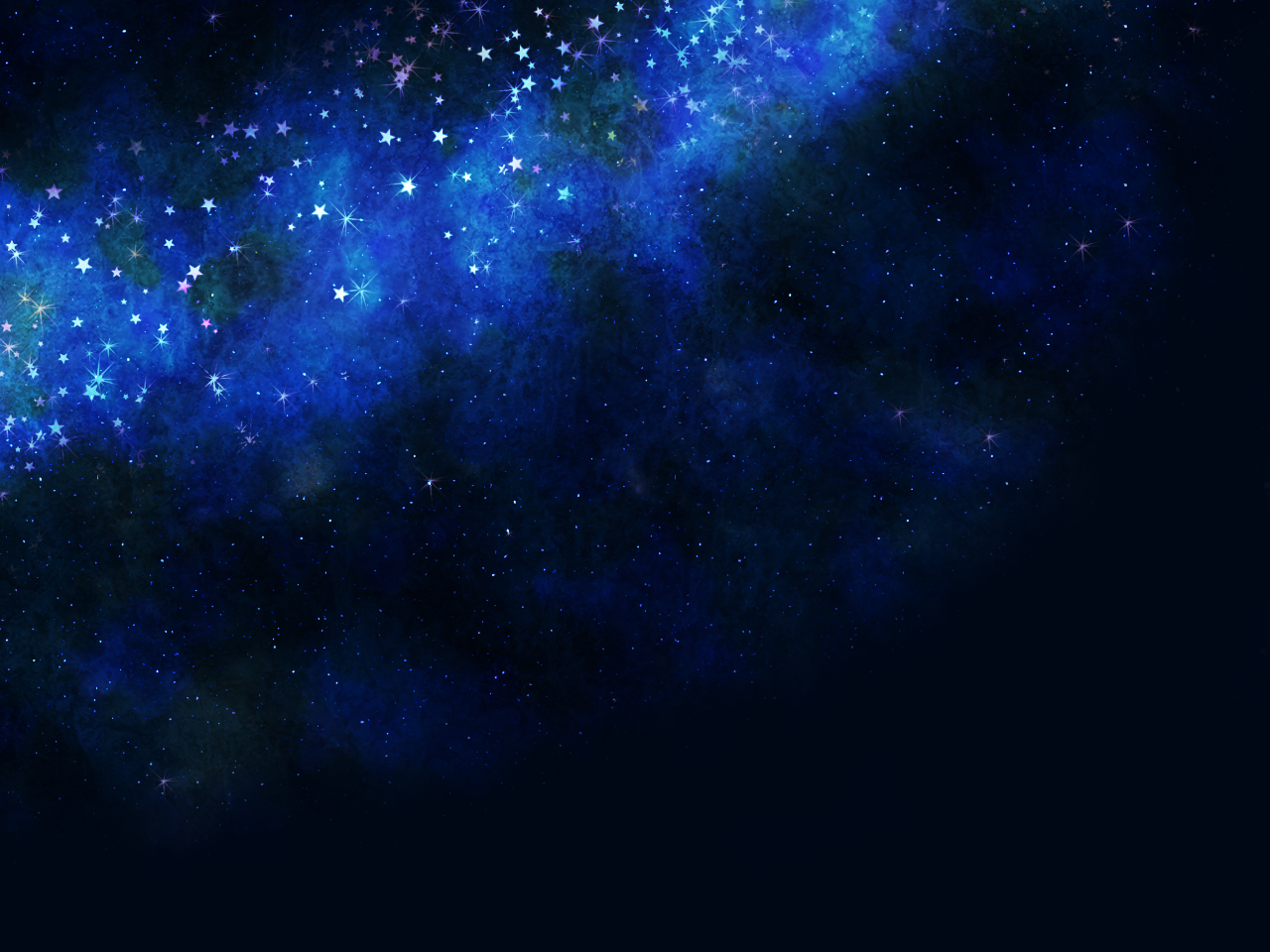「翔ちゃん、大丈夫ですか?」
「大丈夫だよ」
那月の言葉にぶっきらぼうに返事をして、翔は舞台袖で深呼吸をひとつ。
あの夜以来、音也には会っていない。顔を見るのも気が引けて、身体の見舞いにも行けていない。
いつの間にか、誰ともなく六人を想定した練習が提案され、大々的に今回のツアーから音也の名前は消えていた。勿論予定されていたセットリストも大きく変わり、音也が居なくてもコンサート自体は問題なく行われるようにセッティングされている。
問題はない。
「今日のコンサート終わったら、皆でお見舞いに行きましょう」
「……そう、だな」
ツアー初日。最初の曲は全員で。全員の曲が幾つか続き、トキヤから順にソロやデュエットが入る。その中で、本来ならば音也と二人の曲をお披露目する筈だった。今は翔のソロ曲に差し変わっている。
未練たらしいと分かっていながら、あの楽譜は鞄に入れたまま控室にあった。一人で練習もした。歌詞だって考えた。いつ彼が戻ってきてもすぐに歌えるように。
それでも、彼が目覚めたという話は上がらない。
「それじゃあ、行きましょうか!」
歓声が聞こえる。身体が熱くなる。気持ちが、歌になってはじけ出したいと叫んでいる。ステージに飛び出せば、そこからはもうアイドルだ。来栖翔の個人的な苦しみは、少し置いておこう。もしも、この歌が届くのならば、
(早くかえってこいよ、音也)
共に、歌を。
歌が聴こえた。
真っ暗な世界に、淡い声。
笑う時も怒る時も全力なくせに、泣く時は少し堪えてしまうから喉を痛めてしまうのではないかと少し心配になる。その温かい声色が、笑顔が、叱る言葉が、音也は好きだった。最近よく涙を見た気がする。その涙は出来れば見たくないのに、拭うこともできなかった。抱きしめて、視界から消してしまうこともできなかった。
ああ、困ったな。
歌いたいんだ、本当は。彼と一緒に、もっと、もっと。彼が大事にしていた歌がある。大事にしていた約束がある。
また、泣くのかな。
それは嫌だな、と思う。
ああ、歌いたい。
この身体は、心は、それだけを求めている。彼とステージに立って、約束を果たすことを望んでいる。何をしているのだろう、自分は。こんな何もないところで、何を。
歌が聴こえる。聴きなれた声で、待っていると言っている。だから、一十木音也は大きく息を吸い込み、口を開いた。
共に、歌を。
「次は来栖のソロ曲だな」
「ん、行ってくる」
「……? 何やら、スタッフが騒がしいが」
「げ、何かあったのかよ」
「彼らもプロ……問題なく任せておけば良いだろう」
「そうだけど」
慌ただしかったスタッフがいよいよてんてこ舞いになり、翔は少し不安げにそれを見ていた。スタッフが何か言い合っているが、あまりよく聞こえない。
それよりも今は目の前のステージに集中しなくてはならなかった。前の曲が終わる。行かなくては、と地面を蹴る。
「来栖さん!」
スタッフの一人が声をかける。
「え?」
しかし、翔はもうステージに走り出していた。
「曲が急きょ――!」
スタッフの声が掻き消え、まぶしいステージで翔は息を大きく吸う。歌う、曲は。
「――!」
そのイントロは予想していた物ではなく、同時にステージの光景も彼の予想に反したものだった。予定されていたものとは違う曲。本来流れる筈だった曲。聴きなれた、大事な曲。そして、待っていた姿。
笑っていた。あり得ないことに、衣装なんか勿論用意されている筈もなく、パジャマのままで。彼のことだから、無理をしてきたのだろう。白衣の男や警備員が反対の舞台袖に見えた。
この曲は彼のパートから始まる。一回もまともに合わせたこともないが、きっと大丈夫だろう。なんとかなる、二人ならば。そう確信して翔も笑顔を見せた。
「今すぐ再入院です!」
ぐずぐずに瞳に涙を溜めて怒り狂うトキヤを、きっと翔は二度と忘れないだろう。少し面白く思ったのは絶対に秘密だが。
叱られている当人は変わらぬ笑顔のまま、軽い口調で謝罪をしている。
ずっと意識が戻らなかったのだ。一曲歌った後、彼はあっけなくステージに座り込んでスタッフに運ばれて舞台を降りた。それでも、楽しそうに笑ってファンに手を振り楽屋へ戻ってきた。彼はそういう男だったと、皆揃って苦笑いをするほかない。
一十木音也は、そういう人間だ。
「びっくりしたよ、起きたら初日始まってるんだもん。慌ててタクシー拾って会場来て、警備員の人に止められちゃった」
「当たり前です!」
「でも、俺翔と約束してたから。スタッフの人に無理行って、曲変えてもらって、衣装もいいやって」
慌てて音也を追ってきた医者が、音也を軽く診察し問題はないと告げる。それでも精密検査は必要で、とにかく体力が戻っていない以上これ以上ステージに上げるわけにはいかなかった。
次の楽曲の準備があると、トキヤは眉を寄せたまま楽屋を後にする。丁度全員の入れ替わりのタイミングなのか、救急車が到着したのか、気が付けば楽屋には翔と音也だけが残されていた。
「お前もう無茶するなよ」
「うーん、できれば最後まで居たかったんだけど」
「お前俺には無理するなって言っておいてなあ!」
「あはは、ごめんごめん」
「まあいい、約束守ってくれたしな……」
「うん」
「だから!」
「うん?」
頬を伝う滴を、温かな手がなぞる。
「もう一回俺様と約束しろ! とっとと身体良くして、凱旋コンサートまでに、帰って来い! それで、また一緒に歌うぞ!」
やっと触れられた。その手を掴んで、翔は音也の瞳を見た。彼もまた視線を返し、少し赤い頬を緩ませてまた笑う。
数日見れなかっただけで、彼の笑顔が酷く懐かしく思えた。もう、この笑顔を失いたくないと思う。愛しく思う。大切に思う。
「うん!」
そんなことは、言葉にしないのだけれど。
Fin.