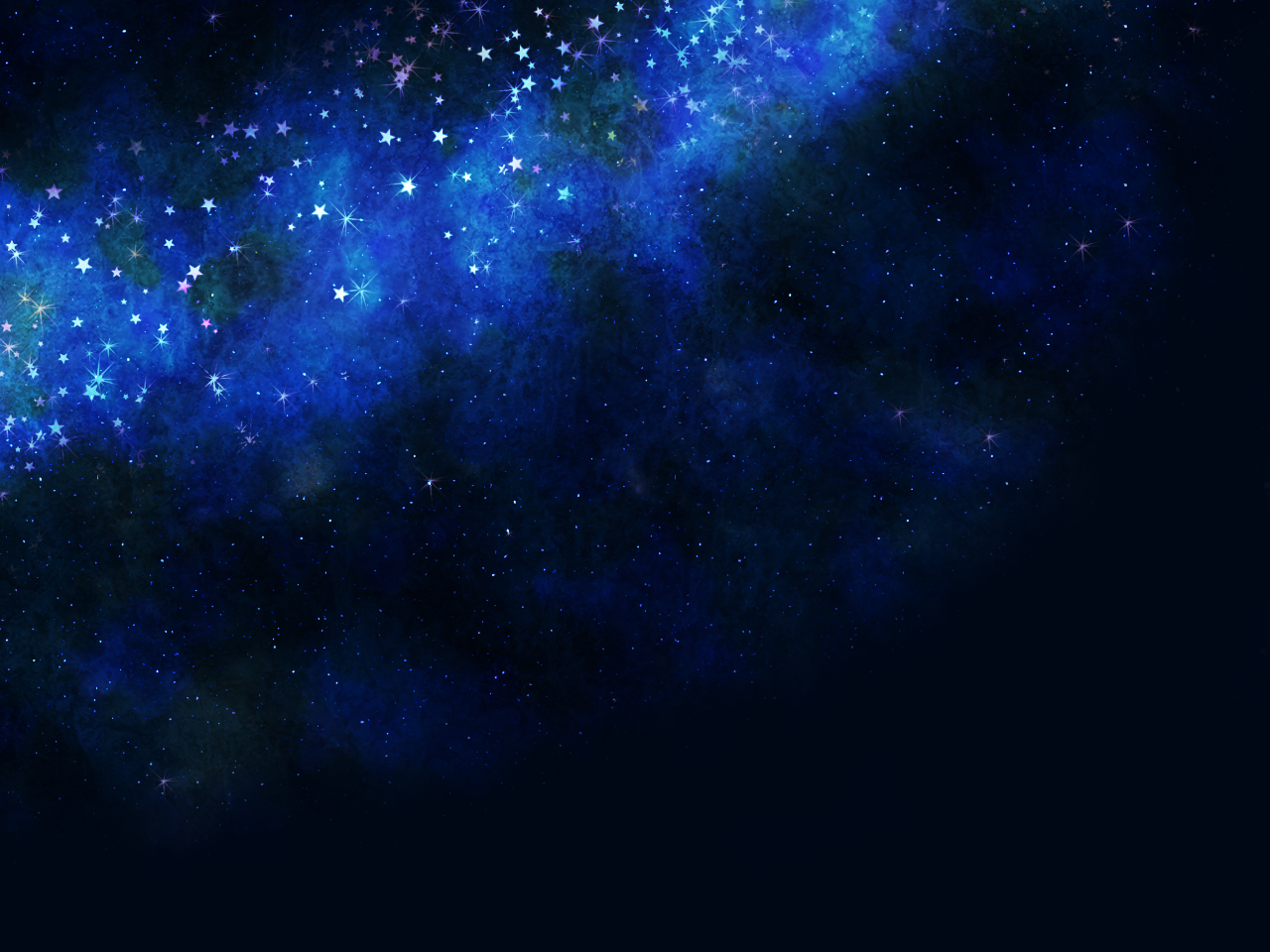|
「あいつら大丈夫かな……」 走っているうちにはぐれてしまったイトコたちを案じつつ、は売店の影で溜息を吐く。初夏の温かな中で走った肌には汗が浮かび、張り付きそうな髪を雑に掻き上げた時だった。 「ねえ」 足音は複数。見つかったかと思い、声の方を見ては顔をしかめた。 に向かって歩いてくるのは、見知らぬ二人組の男。 服装を見るに、生徒でもなく普通の客だろう。 「一人? 今日学生多いけど、遠足か何か? 「いいねえ、学生は。暇ならちょっと面白い所行かない?」 瞼を微かに落とし、綺麗な形の眉を寄せて、は彼らをじとっと睨む。 「そんなチープな台詞、仕事でも聞かなかったぞ……」 「ん? 何か言った?」 ぽつりと呟いた声は、男たちに届かなかったようだ。 はあからさまに重い溜息を吐くと、彼らを無視して去ろうとした。 その手を男が掴み、はいよいよ苛立った様子で彼らをきつく睨む。 「俺、男だけど」 「えー、そんな嘘つく程いや?」 「怖くないよ〜、オレ達!」 そう言いつつ、掴む力が強くなったことに気付く。 「痛っ……」 「あー、痛かった? ごめんね?」 「素直になれば、優しくしてやるんだけどなあ」 「おい、離せよ!」 「あっちに行ったら、離してやるよ」 「はーい、あっち行こうな〜」 力では敵わない。 抗うための力が欲しかった。それでも、その力を鍛える時間もなければ、それが許されるような境遇でもなかった。 しなやかに、柔く、白く、愛おしく。 それだけが、に求められ、また許された生き方だった。 「この、離――」 「なあ、にーちゃんら」 の言葉を遮ったのは、聴きなれないイントネーションのけだるげな声。 それは、ここ最近よく耳にする声だった。 「忍足……」 男たちの影から、そこに立つ彼を見る。 にこりと笑顔で立つ忍足は、まるで大丈夫だと言うかのようにひらひらと手を振った。 それだけで、少し安心する。 だからは軽く頷くと、力を抜く。 「そいつ、うちの後輩なんですわ。男子テニス部の。かわええやろ? でもなあ、にーちゃんらに渡すわけにはあかんのや」 「はあ? なんだ、てめえ」 「とゆーわけで、な?」 軽やかな足音が、の耳に入る。 向かってくる。真っ直ぐに。 「お、おい!」 「危ねえ!」 まるで体当たりでもするかの勢いに、思わず男たちはぱっとその場で身を翻す。 開いた視界で、忍足はにこりと微笑むとの手を取った。 だから、も彼の勢いに乗って走り出す。 「あ、待て!」 そんな怒声は、気付けばはるか後方に置き去りにしていた。 「殴り飛ばすのかと思った!」 「んなことして問題になったら、大会出れんくなるやろ!」 「そうだな!」 笑いながら走り、売店から遠く離れた頃、2人はやっと足を止める。 流石のレギュラー部員との並走はかなりきつかったのか、立ち止まると共にはがくんと地面に崩れ落ちた。 それでも、無性に逃げてきたことが面白くて、笑いが止まらない。 そんなに、忍足は自動販売機で水を買うとそれを差し出した。 「あー……ありがと、忍足」 「こらこら、先輩やろ?」 「……忍足先輩」 「はい」 イケメンがふわりと微笑むのは、流石に絵になる。 多分、女生徒が見たら卒倒してしまうのだろう。 真似でもしたら、少しは自分も男らしくなれるのだろうか……。 「なんや、そない見て。見惚れたん?」 「いや、かっこいいなって……おい、にやにやするな!」 「いやいやいや、無理やろ。そない唐突に『かっこいい』とか!」 「はあ、やっぱ変な奴だな」 「……」 「……じゃあ、俺行くわ」 「行くな行くな」 逃げようとした腕を掴まれ、芝生に再び座り込む。 その手はすぐに離してもらえたが、何とはなしに逃げづらくは膝を抱えた。 「聞かないんだ」 「聞かへんな」 「追ってきたから、問い詰められるかと思った」 視線は重ならない。 ただ、言葉だけが二人を繋いだ。 「そもそも登場から迷子で、五月に跡部のコネで転入してきて、何もないやなんて誰も思ってへんて」 「う゛」 「せやから、もう逃げんくても、ええねんで」 「……ん」 小さく頷いて、は少しだけ視線を上げる。 広がる快晴。眩しい太陽に、今は照らされているのだと。 back |