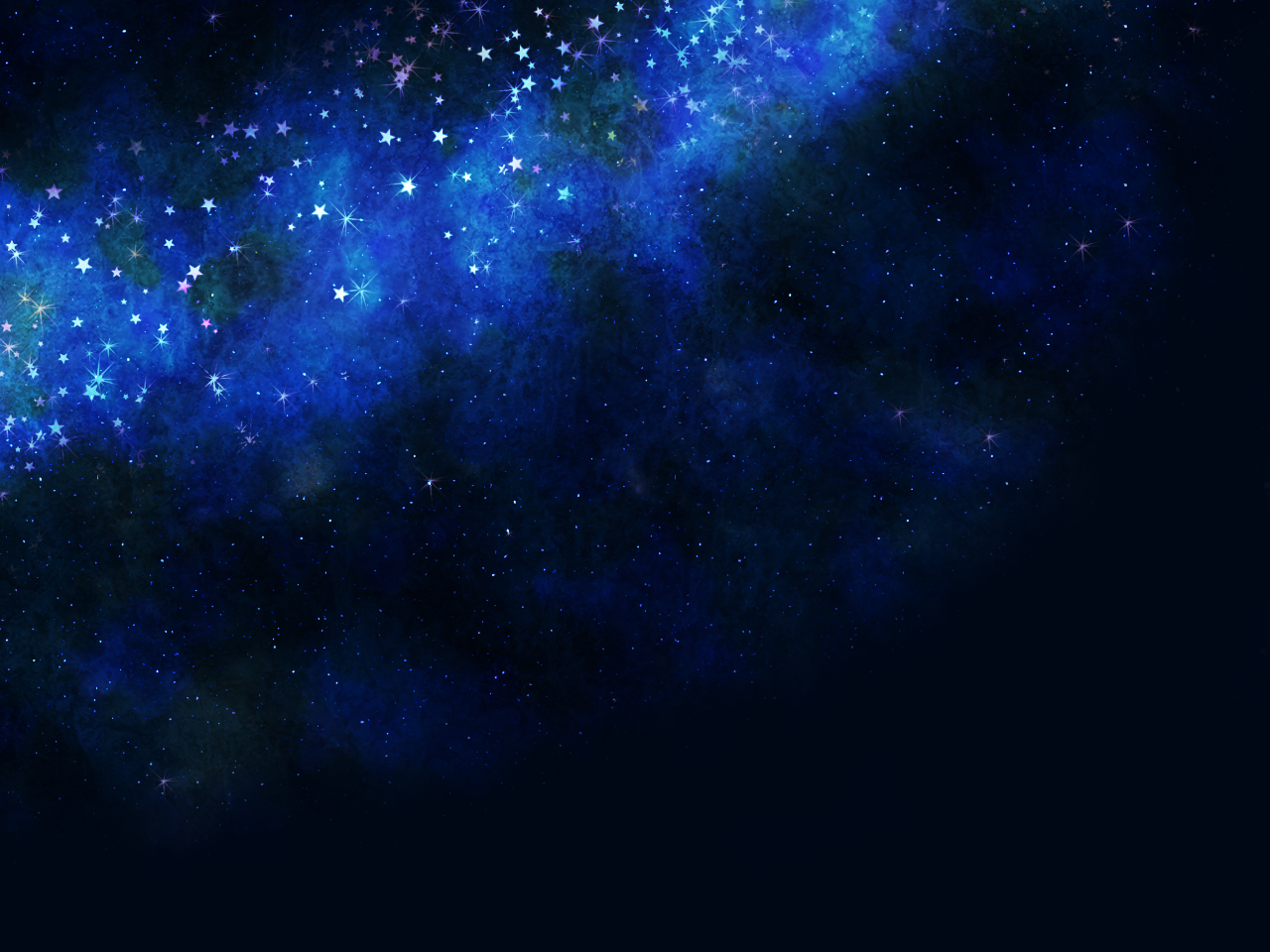|
「すっごい視線を感じる」 碧の不機嫌な声は、賑やかな会話の波にかき消されて消えた。 総勢十二人の生徒が昼食を広げる光景は、流石に注目の的である。 濯たちの知り及ぶことではないが、テニス部のメンバーはその個性と部活動の優秀な成績から有名人でもあるのだ。 「今度、コートに練習見に行ってもいい? オイラ、真田の練習見たいなー!」 「大歓迎だよ」 「何故幸村が答えるのだ……」 「ほう。功乃の弁当は冷凍食品も使っていない弁当だが、親御さんは随分料理上手なんだな」 「ああこれ、たっくんが……えっと、濯くんが作ったんですよ」 「色々あって今一緒に暮らしてるんだよ俺たち」 「なーんか、その言い方やらしいっスね……!」 「も居るし、僕も居る。大体、そういうのは濯にはまだ早いよ」 「さらっと童貞バラされとる」 「こら、仁王くん。女性の前ですよ」 「ジャッカルのおかずもーらい!」 「あ、おい!」 賑やかな食事に不慣れではあるものの、不快ではない。四人はテニス部の面々と会話を交わしながら、彼らの名前を憶えていく。 「和水たちは……えっと、兄の方の和水な。部活どうするかもう決めたのか?」 「いいよ、濯で。もしくはたっくん。も居て紛らわしいからなー。碧のことも碧って呼んでやってくれ」 「また勝手に……僕たち、結構突然転校が決まったから、まだ何部があるのかも知らないんだ」 溜息まじりでジャッカル桑原の問いかけに碧が答えると、お茶を啜っていた柳が頷く。 その動作の意味を理解したのか、仁王も一緒に深く頷いた。 「そういうことならば、テニス部に入らないか?」 「テニス部?」 「せっかくこうして知り合ったんじゃしな。それにまあ、都合が都合じゃろ……近くにおった方が、力にはなれると思うんじゃが」 「仁王は彼らの家庭のことを知っているのか」 「ん、まあ。色々あってのう」 真田の問いかけをはぐらかしつつ、仁王は「どうじゃ?」と胡散臭い笑顔を浮かべた。 その光景に、柳蓮二は箸をコトリと置いて軽く頷く。 「何か思う所でもあるんスか?」 それに目聡く気付いたのは、惣菜パンを齧っていた二年の切原赤也だった。 柳は人差し指を立てて赤也に黙るよう指し示すと、ちらりと背後に聳える校舎を見た。 「えっ……ああ」 それで彼は全てを理解したのだろう。 はそのやりとりに首を傾げながらも、うんうんと唸って悩む濯の顔を覗き込んだ。 「うーん、でもなあ……部活に入ると、皆の飯とかがなあ……」 「たっくんの好きに決めていいんだよ。私だって、家のことちゃんとできるよう頑張るし」 「ねえ、兄貴」 いつの間にか騒ぐのをやめていたが、と同じく濯の顔を覗く。そしてその手で、彼の手をぎゅっと握って。 「あたしだってそこそこ料理は出来るし、それに……それにさ、碧だって洗濯機のスイッチくらい押せるし、だって多分お風呂洗いくらいはできるよ」 は、彼が元の世界にあっても部活動をしていないことを知っていた。 同時に、彼がそういった普通の学生としての生活に憧れていたことも、知っていた。 普段のおどけた口ぶりとは違い、真っ直ぐと兄の目を見て言い放つにも碧も反論をしようとは思わなかった。 それ以上に、の濯を想う気持ちには深く同意を示していた。 「だから、やりたいって思ったら、あたしは兄貴にテニスしてほしいって思う」 それに、そしたらいつでも真田に会えるしね! などと、誤魔化すようにが笑うと、濯は困ったような笑顔で彼女の額にデコピンを一発。 それから呻く彼女の頭をわしわしと撫で乱すと、碧をちらりと見やる。碧がこくりと頷くのを確認すると、濯は手を真っ直ぐ突き出した。 「不束者ですが、宜しくお願いします!」 その手を、部長である幸村がぎゅっと握る。 「うん、よろしくね」 濯の手を握りながら、をにこにこと見つめる視線を無視することにしたのだろう。は良かったと言いながら食べかけの昼食を再開させた。 「ところで、テニス部に入部するならばこういうのはどうだろうか」 会話の終結を見届けた柳が、突然切り出す。 「濯が真田と試合をして、負けたら残りの三人もマネージャーとして入部……とかな」 柳に視線が集まり、それぞれが驚きの色を浮かべていた。 濯はぶんぶんと首を横に振り、無理であると叫ぶ。 「んなの、俺が負けるのが確定じゃねえか!」 「家のこととか、あるじゃろ……」 「俺は良い考えだと思うんだけどなあ。ねえ、?」 「エッ、んっんー? 真田とお近づきになれるのは嬉しいんだけど、ゆっきーが怖いんだよなあ!?」 を中心に再び騒ぎ出す面々だったが、その騒ぎの中はちらりと碧を見る。 自分たちのことにここまで首を突っ込まれて、短気でヒステリックな彼がまた苛々しているのではないかと不安に思ったからだった。 だが、彼の様子はあまりに―― 「僕は構わないけど」 普通、だった。 「え?」 涼やかな表情はそのままに、碧は綺麗な顔でにこりと微笑む。 普通というより、むしろ機嫌は良さそうだった。 「さっき仁王が言っただろう。傍に居た方が良いって。濯だけで行動させるのもアレだし、多分これからも困ることは多いから、力になってくれる人とは仲良くすべきだ。それに、そうならば部活を手伝うのも道理だろう?」 いつの間にか食べ終えていた濯お手製の弁当を片付けながら、碧は周囲の驚きも気にせずに自身の考えを語っていた。 「まあ、僕らとしても家事の時間が減って家がどうなるか分からないけど。そういうところを加味して、濯が真田と勝負するっていうのは悪くないと思う。濯なら、もしかしたら勝てたりするかもしれないし」 「俺テニス未経験者!」 「色んな部活の助っ人で小銭稼いでたくせに、よく言う」 「う」 「いいよ、濯。どうなっても構わない。僕だって迷ってるんだ、ここで何を成すべきか……だから、その道を、きみの腕に任せてもいいかなって、そう思ってる」 「どうしよう、碧が素直だよ。兄貴、弁当に何入れたの」 「おおおおお俺じゃねえよ!」 「二人共、聞いてる?」 涼やかな表情に、さっと影が走る。 「そういうわけだから、いいよね、?」 「え、私は……碧が良いなら、それでいいよ。私だって、迷っているから」 「じゃあ、そういうことで。真田、よろしくね」 「えええ」 「む……俺は構わんが、本当に良いのか?」 「うー、もう、分かったよ! 試合すればいいんだろ!」 濯は立ち上がると、頭をガシガシと掻いて仁王とブン太の首根っこを掴む。 「うわっ」 「まじか」 「おい仁王、丸井! 放課後までにルールとコツ教えろ!」 二人を引きずり、濯は教室へと去っていった。 残された面々は苦笑いを浮かべながらも、残りの昼食を綺麗にして各々くつろぎ始める。 濯が居なくなっただけだというのに、途端に居心地の悪さを感じ、も荷物をまとめて立ち上がろうとした。 「あれ、仁王は?」 ふと、背後から飛んでくる声。 「教室だ」 「なんだ、入れ違いか。教えてくれてありがとう、柳。赤也、お昼終わった? 時間あるなら、軽く打ち合いしよう」 「いいっスよ!」 立ち上がる赤也。彼が駆け寄ったのは、黒のショートボブに猫のような印象を受けるツンとした瞳の少女だった。体型は小柄な方だとは思う。とはいえ、のような幼さは無く、むしろスカートの下の脚を見るに、身体は鍛えられているようだった。 「じゃあ、赤也借りてくね」 「怪我をしないようにな。もうすぐ、昼休みも終わる」 「分かってるよ、じゃあね!」 たちには目もくれず、去って行く彼女。 その背を見送り、も立ち上がった。 「、戻るん?」 「うん。次の授業の範囲を確認とかしておきたいし」 「ワオ、なにそれ凄い」 「もやった方が良いよ。簡単な予習で、全然変わるんだから」 「う……」 「じゃあ、先輩方。お先に失礼します」 「ええ、また放課後に」 丁寧にお辞儀をして、は中庭を後にする。 突然やってきた世界は元の世界と変わらないような普通の世界で、それでも大きく違うことがあった。それは、誰も彼もが自分たちに手を差し伸べてくれること。 息苦しい競い合いしか知らなかったの知らない優しさ。それが自分たちに向けられることに、戸惑いもするが何よりも安堵する。 失った黒は戻らなくても、この戒めのようなグレイの髪のような苦しみはもしかしたらもう無いのかもしれない。そう思いながらも、は自分を失った両親が何を思っているのか、そのことが少しだけ気がかりだった。 back |