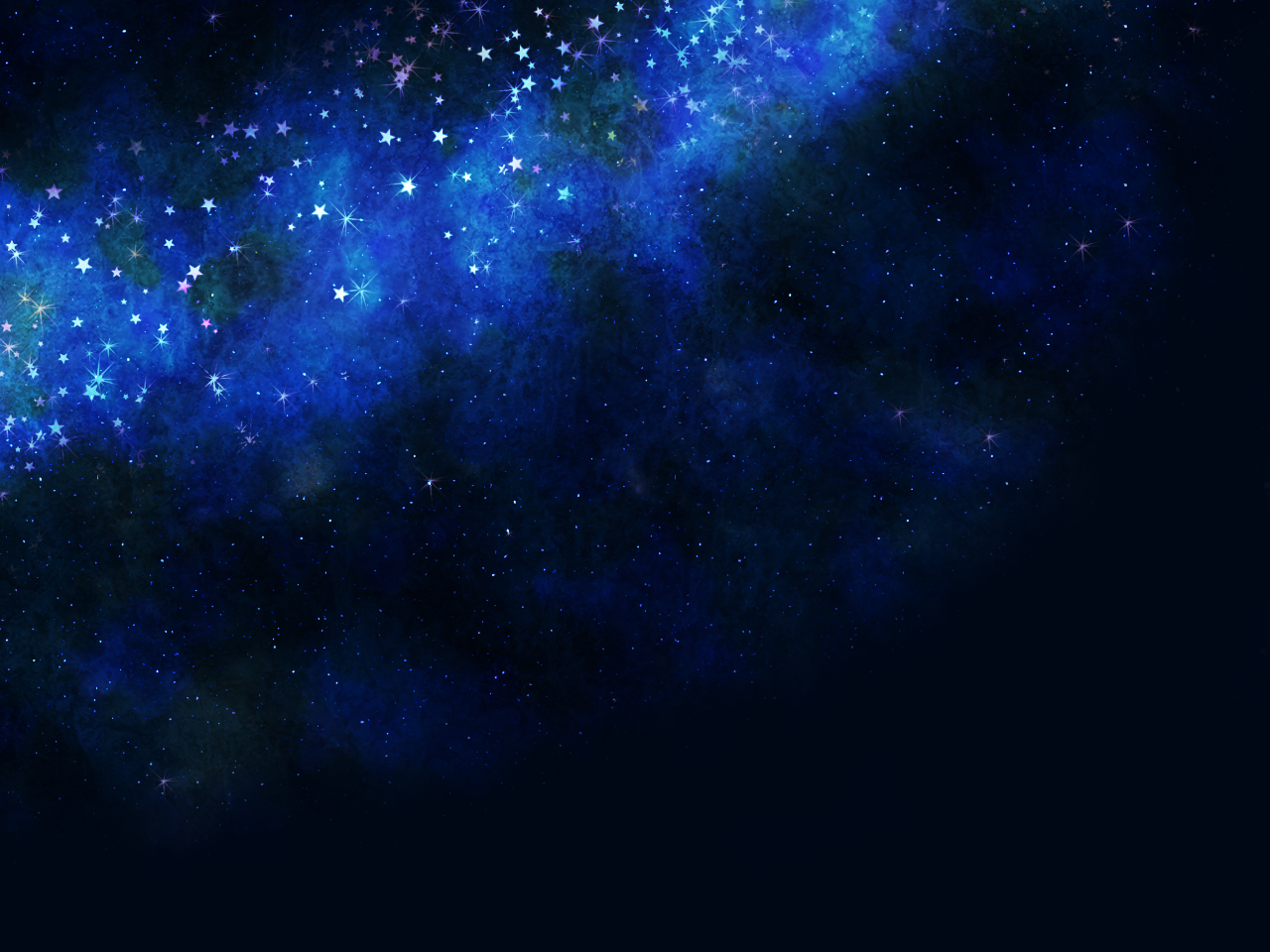|
幸いにして借りたテニスシューズのサイズも合い、初めて握ったラケットの感触も悪くない。 昼休み後半に聞いた話では、立海大附属中学のテニス部は全国常連……それどころか、大会優勝もざらの部だという。 その副部長に、濯はこれから挑むのだ。 「出来レースにも、程があるだろ……」 溜息は漏らさない。幸せが逃げると聞いたことがあったから。 少し前の自分ならば気にならなかっただろう。逃げる程の幸せも、もう残っていなかったから。 でも今は違う。方法は何であれ、今は人並みの生活を送れている。誰も、自分たちの出自や異様さを知らない。誰も、責められる必要がない。 ずっと願っていた、夢のような場所。だから、この幸せだけは逃がすわけにはいかない。 「濯」 「悪いな、碧。お前の勉強の時間とか、奪っちまうかも」 「言っただろう、僕はすべきことを迷っている。結果は――目に見えてはいるけど、でも、濯ならもしかしたらとも思う」 「ホント、熱でもあるんじゃねえの? 碧がそんなに俺のこと褒めるとか……大丈夫か?」 「本当に失礼だな。この僕が褒めてあげてるんだから、素直に受け取れないの?」 「痛い痛い、つねるな! 悪かったって!」 「……濯は、知った方が良い」 「うん?」 「負けても良い戦いがあること。その背中に守ってきたものが、どれだけ強く育っているか。濯は純じゃないから、ちゃんと、知った方が良い」 「俺が純じゃないって……んな当たり前のこと……」 「分からなくてもいいから。じゃあ、僕はたちと向こうで試合見てるからね」 「おう」 親友に手を振り、コートへ駆け出す。 染めた金髪が陽の下でより明るく彼の存在を証明する。 「兄貴ー! 真田ー! がんばれー!」 「はどっちの応援してるのよ……」 「どっちも! でも、どちらかといえば真田!」 少し離れたところから、妹と妹のように可愛がっている後輩の声がする。 会話の内容に、濯は後で妹のことを小突くことを決意して視線を対戦相手へと向けた。 「とんだことになったが、試合である以上手加減はせんぞ」 「ああ、それでいい。それがいい。悪いな、真田」 「構わん。他の部員も乗り気なのはあるが、何より我が部の戦力が増えるならばそれに越したことはない覚悟をしろ、和水」 「だから、濯でいいって」 「む」 「和水は二人。俺と、あのバカ妹。あいつバカだから、和水だとあいつも反応しちまうぞ?」 「そうか、では――濯、始めるか」 「ああ」 審判役の柳が声を上げる。 副部長と謎の転校生の試合の噂はいつの間にか広まり、ギャラリーも熱を増す。 試合の立ち上がりは上々。真田にくらいつく濯のプレイに、部員たちは微かな驚きを見せた。 「負けてもいいよ、濯。いや……負けてよ、濯」 ついに濯が真田から1ゲームを奪い、真田も驚き混じりに微かに笑みを見せる。 「負けてくれたら、後は全部、僕が勝たせてあげるから――」 試合終了の声が響く。 結局濯が真田から奪えたのは1ゲーム。だが、それでも各ゲームの試合運びは接戦なことも多く、二人がきつく握手を交わすとギャラリーは歓声を上げた。 「これで、たちもテニス部だね」 「おおう、ゆっきー……」 「お前幸村くんに何したんだよ……まあ、これからシクヨロ」 「テニス部は忙しいかと思いますが、どうぞ宜しくお願いしますね」 「はい、柳生先輩」 「俺とも宜しくしような」 「仁王、功乃が凄い顔してるぞ……」 疲労困憊といった様子で、濯がベンチにふらりと近づく。 それに気づいた碧は、タオルとドリンクを片手に彼に駆け寄る。 「お疲れ様」 「ん、悪ぃな。本当に負けちまったわ」 「構わないって言っただろう?」 濯はその時、背中がぞわりと逆立つのを感じた。 碧が笑みを浮かべる。 それは見慣れた筈の少年の、あまりに美しい笑顔だった。 「跡部だけじゃなく、君にも感謝しなきゃ。僕に、方法をくれたんだから」 「あお、い?」 「僕の成すべきこと、決まったよ」 満面の笑みで、碧は。 「一緒に青学を倒そう、濯」 to be continued. back |