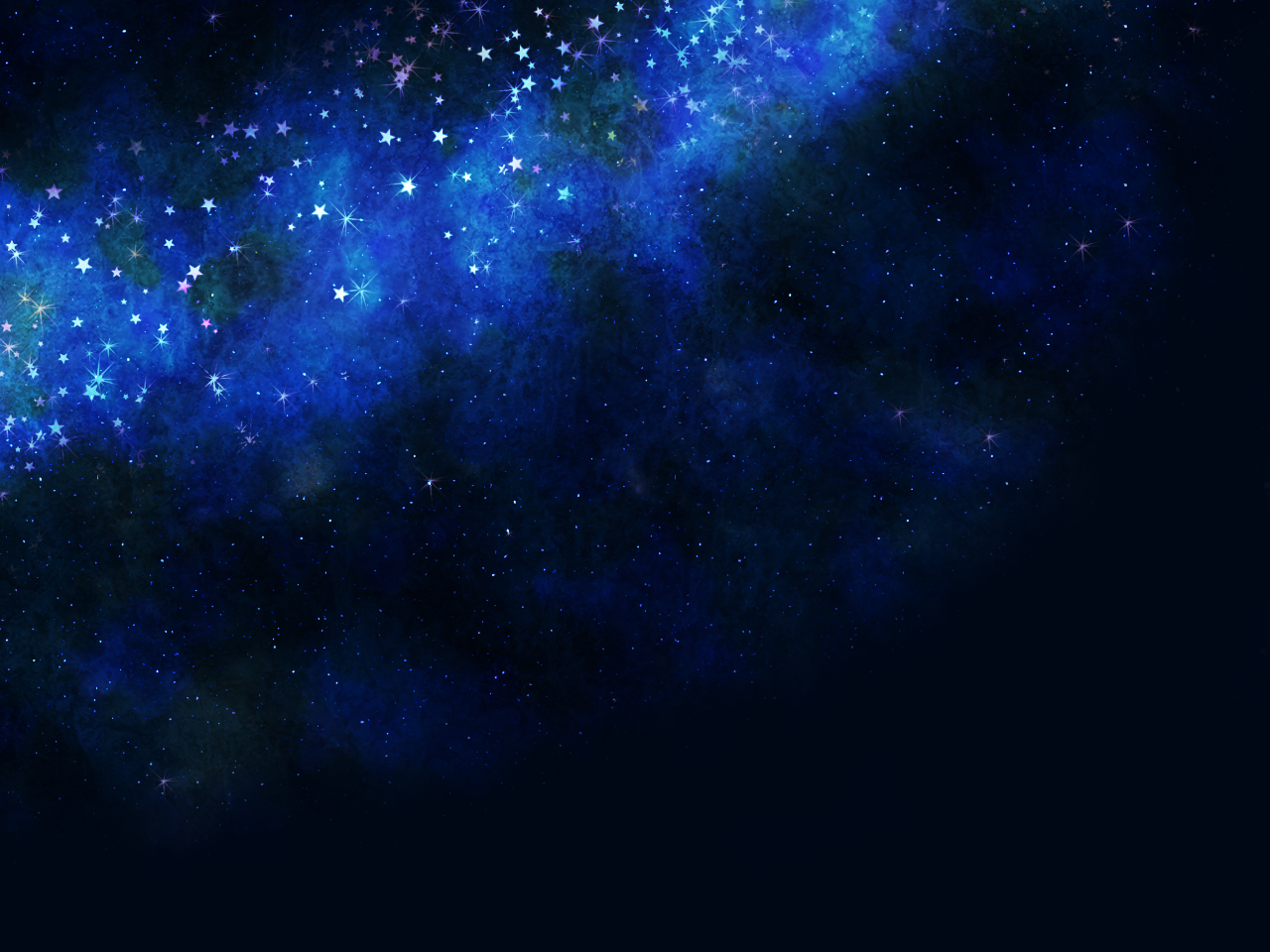|
テニス部の部室は、予想に反して小じんまりとしていた。と言っても併設されたパソコンルームなどを見ると、通常のそれとは大きく異なっていることは間違いない。しかし、二百人以上を抱える部活動の部室としてはやや手狭である。跡部曰く、この部室はレギュラー専用のものらしい。その説明を受け、は納得をしつつもその格差に不満を抱いた。 「現状に満足してるような腐った奴はうちには居ねえよ。この部室も一つの象徴だ。ここを目指し、各々が努力する。だからこそ、うちは強い」 「ああ、そう」 そこまで興味もないと言いたげには会話を絶ち切る。そもそも年上の彼に敬語を使う素振りもないあたり、跡部に対しての彼女の考え方はぞんざいなものだ。 「まあいい、今ここに居るのがそのレギュラーってわけだ」 の態度を咎めることもなく、跡部が手を広げる。部室には、見知った顔やそうでない者も含めて八人の男子が並んでいた。彼らを前に、たち四人は思い思いに突っ立っている。 「お前らが関わるのは大体この八人だな」 「それもレギュラーの特権か?」 「それ以上に仕事量の問題だ。二人で二百人の面倒を見れるのか?」 「は、ちょっと待て!」 「抗議……抗議や!」 跡部の言葉に違和感を覚えたのはだけではなかったようで、ずらりと並ぶレギュラーの中から眼鏡の少年が抗議の叫びをあげた。彼の顔には見覚えがある。この世界で、この学校で初めて出会った人たちの一人。どうやら純によって破壊された眼鏡は既に問題なく修復済みらしい。 「二人ってどういうことや、癒月は男子ちゃうで? 部員にはなれへ――」 は椅子が宙を飛ぶのを初めて見た。 「マネージャーはと癒月だ。残り二人は部員としてテニスをしてもらう」 何事もなかったように説明を続ける跡部の横で、により椅子を投げつけられた忍足が倒れている。 「俺も純もテニスなんかしたことないですけど」 「覚えればいい」 「冗談やってん……」 「あとで謝っとけよー」 呆れたは、しゃがんで床に倒れる忍足に言葉を投げる。今のは確かに彼が悪い。 そんな二人に一切気をかけることはなく、純は唇を尖らせた。 「人手が足りないなら、マネージャー募集すればいいのに。さっきのお姉さんたちだって、頼めば何だってしてくれそうだったけれど」 「そうしてレギュラーの私物がごっそり無くなったことがあってな。その点、お前らならそんな心配はない。何せ、俺様無しでは生活もままならないんだからな」 クツクツと厭味に笑い、跡部は純にジャージを放る。 「それにな、今レギュラーの多くは三年だ。次を見据えるのも部長の勤めでな。お前らには、いずれレギュラーとして部を支えてもらわなきゃならねえ」 「はあ?」 「経験こそ差はあるが、俺様の眼力に嘘はねえ。素質は申し分ない」 「……はあ、俺が高く買われるのなんて珍しい。まあ、の為だと思ってこの件には従うよ」 誰が決めたわけでなく、四人の中で決定権を握っているのは純だった。短絡的な所のあるや、純に絶対の信頼を置く幼稚なは元より、比較的冷静なでさえ純の決定に異を唱えることは珍しい。特別反対する理由がないというのも確かだが、こうして四人はテニス部への入部を正式なものとしたのだ。 本来の名前の意味が薄れていく感覚をどこかに覚え、足元が軽くなる。自分を縛る家ではなく、これからこのテニス部が自分の背負う物だ。悪くはない。振り返って懐かしむ程、過去は優しくなかったから。 back |