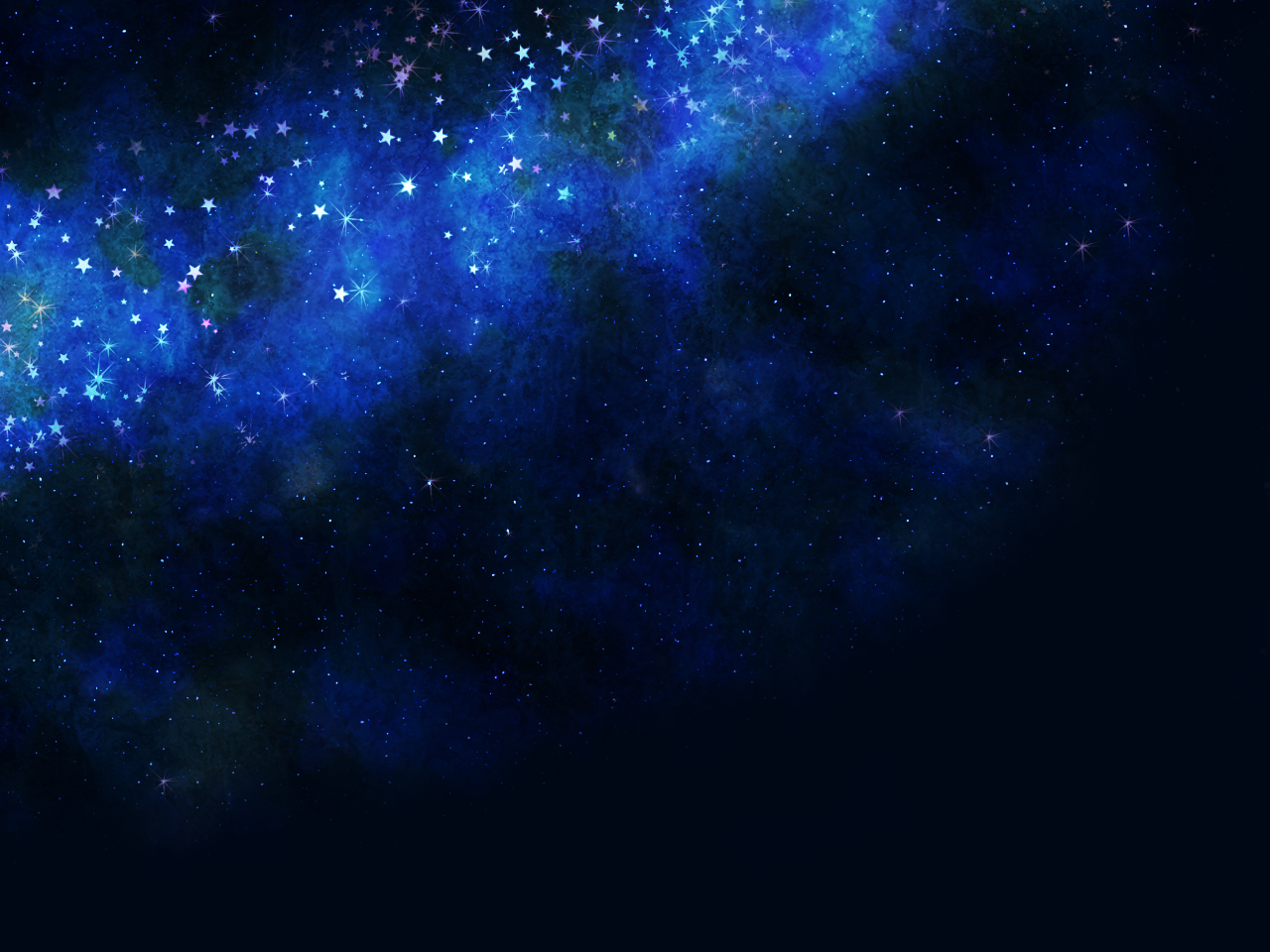|
携帯電話が時間通りにアラーム音を鳴らす。ローテンポの音楽に、は意識が覚醒してゆくのを感じた。朝日を瞼越しに浴び、目をぐしぐしと擦りつつも足先までをぐっと伸ばす。縮こまっていた身体全体に酸素がぐいと行き渡り、小さな身体はとたんに熱を帯び出す。 「ん……純……朝だよぅ……」 顔を横に向け、同じ布団で眠る双子の兄の顔を撫でた。同じ色の髪に指を通して、少しだけお姉ちゃんになった気分だ。 「やぁ……後5分……」 「だぁめ……お布団畳めないでしょう?」 寝ぼけて互いに舌ったらずになっていることがおかしくて、二人は顔を見合わせて笑った。以前ならこんなことはあり得ない。だが、こうして檻のようだった家を出た双子は自由の御子だ。生まれた時は同じだったのだ、引き離されていた方がおかしい。それが二人の共通の考えだった。 「が来る……」 足音が聞こえたのか、純が呟いた。には聞こえない足音も、純には聞こえる。五感の発達、秀でた身体能力、明晰な思考回路。紫凪純が持て余す才能は、異常に近いものがあった。 神童、以前誰かがそう言っていた。くだらないと純は思う。神だろうが人だろうが、そこにが居なければ、自分に溢れた才能など無いも同然だ。何でもできる兄と、何もできない妹。それがこの双子の関係。絶対的にかみ合う凹凸。存在意義は、ここに在る。 「朝だぞ、起きろ!」 襖が荒々しく開かれ、威勢良くが部屋に踏みこんでくる。真新しい畳の香りがふわりと漂い、双子はゆっくりと起き上がる。はそれを急かすこともなく見守り、満足そうに笑った。 「ちゃんおはよー」 「ん、おはよう。さ、早く顔洗ってこい。が今朝は和食にしてたぞ」 この家では現在、が食事を担当している。にその役割は到底無理として、多彩な純も経験がない料理となれば中々難しい。毎日のことでもあり、その手際の良さからもはごく自然にその役割を受け入れた。もそれなりの腕前であるが、短気な彼女がこの生活に馴染むまでは料理は一人でやった方が問題も少ない。 「ー、おはよぉ……すー……」 「寝るな寝るな、立ったまま寝るな」 台所に顔を出し、は覚醒した筈の意識をゆっくりと手放そうとする。それを見かねたは、真新しいエプロンで手を拭きながらを洗面所へ誘導した。 跡部が用意した二階建ての日本家屋は、氷帝学園の敷地からそう遠くはない住宅街にあった。一階には居間や台所、風呂場やトイレといった生活の中心となる部屋が並び、二階には三つの和室がある。双子はセットで少し広めの部屋を貰い、とも自室を貰いうけた。それぞれが以前とは正反対の生活を送り、それに慣れはしないものの快適であることには間違いない。 「ったく、金っつーのはある所にはあるもんなんだなあ……」 そんなこと、辻宮は十分に知っている筈だった。忘れていたわけではない。ただ、この数日の慌ただしさの中で考える暇がなかったのは確かなことだ。考えなくなっても、この身体が綺麗なものになるわけではないのに、思い出すことは酷く汚らわしい。 それでも、今は、これからは。 「この未来は、誰にも汚させない」 To Be Continued. back |