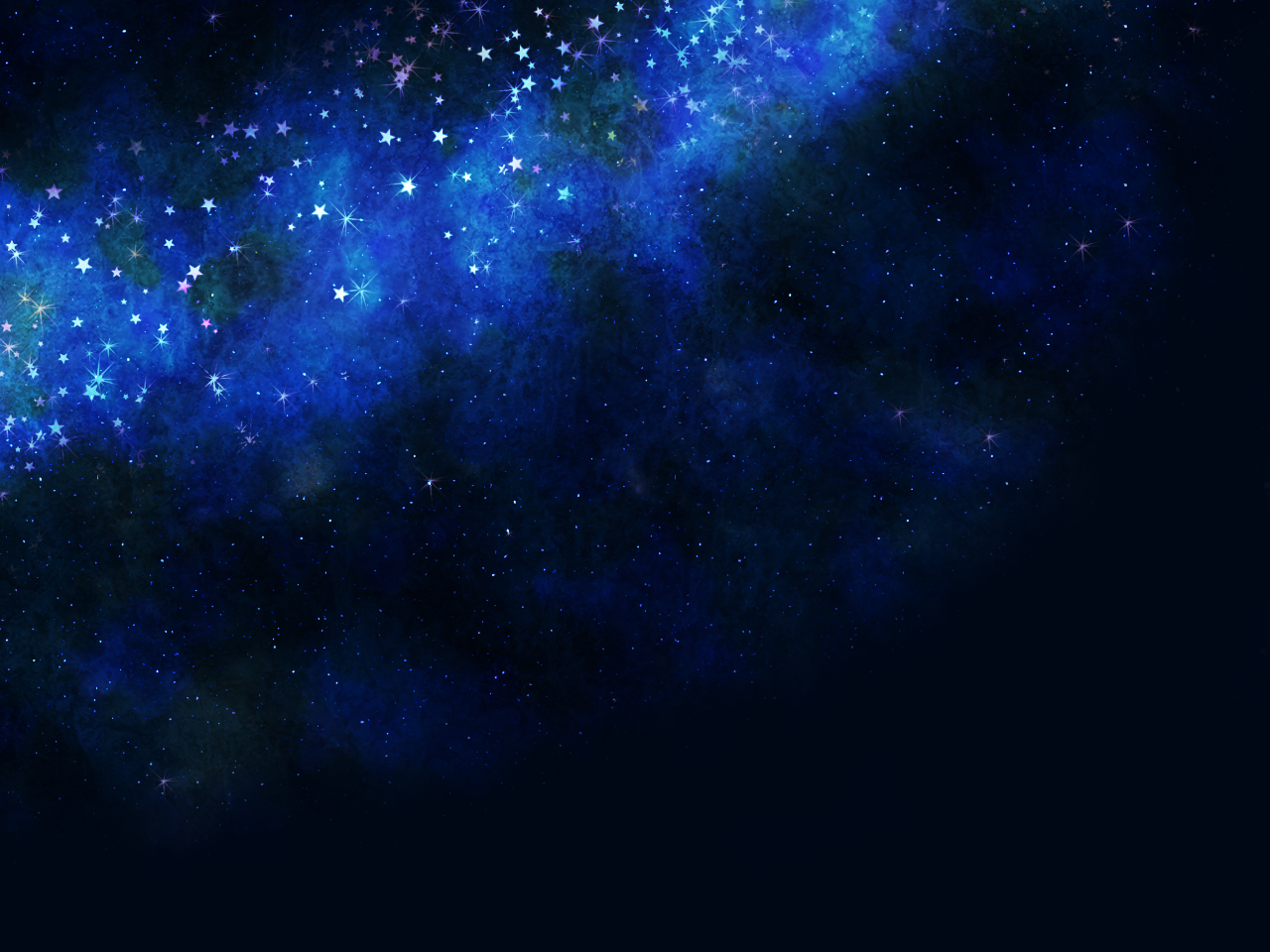|
紫凪は愛されている。守られている。酷く局地的に。 本人はそれを感じているが、そこに違和感や特異性を感じられる程ではなかった。だから、今こうして目の前で自分を見降ろしている女生徒たちが何を思いに敵意を向けているのかを理解することはなかった。 「ちょっと、なんか言ったらどうなのよ」 きょとんとするにしびれを切らした女生徒が、口を開く。敷地も校舎そのものも広い氷帝の、人気のない校舎裏。高い校舎に日差しは遮られ、特有の湿度を孕んだ空気を吸い込み、厚い敵意に押しつぶされないように喉の熱を吐き出した。 「な、なんかって……?」 ようやく出た言葉はどうやら彼女たちの意にそぐわないものだったらしく女生徒たちの眉間に深く皺が刻まれる。 授業も終わり、テニス部の部室へ向かおうとしていたは見知らぬ女生徒に半ば無理やりこの場所に連れてこられていた。の目から見ても、自分を囲んでいる女生徒たちは十人を軽く超えている。人に取り囲まれることは昔からよくあったが、こうも露骨に敵意を向けられるのは初めてだ。 「大体どういうつもりよ。転校早々に、何調子に乗ってるの?」 「どういう?」 「とぼけないでよ。跡部様に様、向日くんにだって親しげに話して……ねえ、あんた自分がちょっと可愛いからって何してもいいってわけじゃないのよ!」 「もうテニス部に関わらないって誓いなさい。それで許してあげるって言ってるんだから」 テニス部に関わるな? この人たちは何を言っているのだろか。にとって、既に跡部は替え難い友人で、自分たちを助けてくれた恩人で、それなのに彼が率いるテニス部に関わるなと彼女たちは言うのだ。 は、先日跡部が車で語ってくれた秘密を思い出す。それを打ち明けて、その上でマネージャーになってほしいと、頭を下げたのだ。 彼を裏切る――そんなことは、 「できない」 アイスブルーの宝石を滲ませるように、丸い瞳に涙が溜まる。 「は?」 女生徒たちが理解できないとでも言うように、を一層睨みつける。 「は! 氷帝学園中等部男子テニス部の!」 与えられた居場所を、好きになれそうなのだ。やっと。生まれて初めて、自分の意思で決めたのだ。 「マネージャーだ!」 叫ぶように――いや実際叫んでいたのかもしれない――宣言をした。 これは、ここで跡部が助けてくれた時に決めた対価で、紫凪がその名を捨てても残る称号で、つまりは今の彼女の存在そのものだった。 「テニス部は、マネージャーの募集なんて――」 「募集はしてねえな。何せ、こいつらで定員だ」 うろたえる女生徒たちは、言葉を遮った冷たい声色に思わず振り返える。 薄暗くじめじめとしたこの場所に似つかない、彼の凛とした立ち振る舞い。王と誰かが形容していたのは、間違っていないように思える。同じ地に立っていながらも、酷く遠く高く感じる彼の瞳はと同じ色をしていた。 「!」 彼の瞳に気圧されている女生徒たちを掻き分け、純がの手を取る。 「あとべ、さ……」 誰かがかすれた声を漏らした。 「散れ」 自分を慕っていることも理解しているのだろう。だが、跡部は容赦なく冷え切った声で彼女たちに命令する。嫌悪と侮蔑、他にも込めようがあっただろうが感情の欠片それだけで彼女たちは絶望したように青ざめて逃げていく。 残ったのは跡部と、と純と。 「、大丈夫か? 教室に迎えに行ったら、連れてかれたっていうから心配して」 「部室も捜したけど見つからないし。そしたら、跡部さんがここかもしれないって」 「は大丈夫……う、景吾こわい顔してる……」 の呟きに、跡部は眉間に手を当てて溜息を吐く。険しい表情は少し和らいだが、それでも笑顔には程遠い。そんな表情も様になるのだから、彼がああも人気なのは頷けるのだが。 「悪かったな。想定はしていたんだが、動くのが遅かった」 「景吾は悪くないよ」 「いや、これは俺の性分だ」 謝られておけと少々高圧的にに告げ、跡部は歩きだす。陰湿なこの場所が気に入らないのか、その歩調は少し早く思えた。 「部室でが待ってるから、俺たちも行こう」 「ったく、なんでアタシがマネージャーなんか」 「仕方ないよ、他に生きる道もないんだし」 純との会話を聞きながら、も後に続く。薄暗い校舎裏から出れば、春の柔らかな日差しがを抱く。この日差しの中が、今のの生きる場所なのだ。 back |