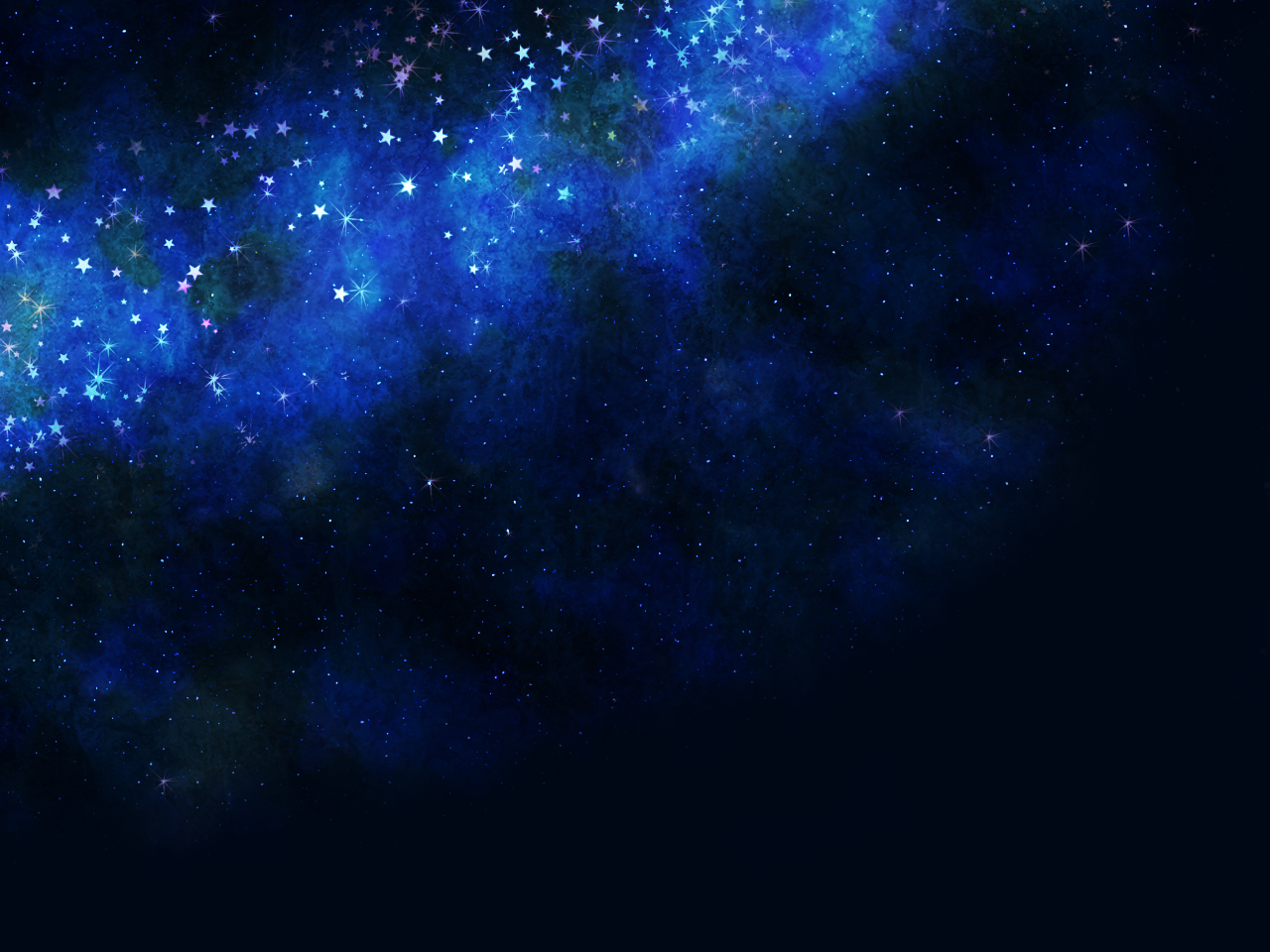|
たちに電話がくる少し前のことである。 功乃は、ゆっくりと目を覚まして辺りを見回した。先ほどまで、駅までの道のりを歩いていたと思っていたのだが、夢だったのだろうか。今は横たわって空を見上げている。 「気がつきましたか?」 「だぁ……れ?」 ぼんやりとした頭で、はうわ言のように呟く。 「柳生比呂士と申します。貴女はいったい……突然現れ、倒れられたので……」 柳生と名乗る人物の言葉を聞きながら、不意にの思考は覚醒した。勢いよく起き上がると、彼と距離をとるように後ずさった。 「誰!」 「ですから柳生――」 「いや、そうじゃなくて! ていうか何で私外で寝て、意味が分からない何これ!」 「おう、! 目が覚めた?」 「ーッ! 何これ!」 キラキラと光を反射させる金髪を揺らし、緩い笑顔で和水はに声をかける。彼女の肩を掴み、は容赦なく疑問を浴びせた。ここはどこなのか、彼は誰なのか、皆はどこなのか―― 「ちょちょちょ、ま、落ち着いてってばー! 兄貴、ヘルプ! ヘルプ!」 の怒涛の質問攻めに、は慌てて兄を――和水濯を呼んだ。興奮したには気付かなかったが、彼女の周りにはちゃんと親しい友人たちが居たのである。 「なんだよ、馬鹿」 「馬鹿じゃないよ、阿保!」 「うっぜ」 「うがああああああごめんなさいごめんなさい放して!」 の顔面を鷲掴みにした濯を見上げ、は理解できな状況に苛立ちを抑えられず軽く地面を踏み付けた。 「落ち着いて」 「碧!」 そのな彼女の様子を見かねたのか、彼女に声をかけた少年――河羽碧。彼の顔を見ると、は少しほっとした様に肩を下ろした。にとって碧は幼馴染であり、厳しい両親に反発したいと思うの唯一の理解者でもあった。彼がこうして落ち着いているということは、今この場この状況に対しての情報を彼がきちんと把握しているということである。彼にも多少ヒステリックな所があることはも知っていたし、何よりは彼を信頼していた。だから、彼の様子にの不安は一気に軽減されたのである。 と濯が騒いでいるのもそのままに、はちらりと柳生と名乗った男子を見た。瞳が見えない位度が強い眼鏡をかけた彼の茶色の髪は七三に分けられ、爽やかな出で立ちだ。真面目そうな顔付きで、どこかの制服であろう洋服もきちんと着ている。 「柳生、柳生、ちょっ、真田は?」 そんな彼に、はきらきらと瞳を輝かせて問いかけた。は少しだけ首を傾た。「真田」という名前はどこかで、聞いたことのある名前だった。そもそも、こうして親しげに話しかけていると柳生は知り合いなのだろうか。別の学校に通うには、の交友関係までも把握してはいない。 「にはまだ説明してなかったね。実は――」 不意に碧の言葉を遮り、 「河羽、見つかった。おまんらの探してる四人、おまんの予想通り氷帝におった」 聞き慣れない声がした。 「ん、分かった。電話はまだ繋がってる?」 「ああ、問題なか」 「借りてもいいかな。向こうの四人はきっと状況が分からなくて困ってる」 「好きにしい」 碧と話す彼の姿に、は眉を寄せた。銀髪、ピンクの髪ゴム、着崩れた制服。所謂不良代表のような出で立ちの彼は、の好まない人種である。真面目な彼女の鋭い視線に気づいた彼は、にやりと笑みを浮かべてに近づくとその顎をくいと持ち上げて、囁いた。 「かわええのう……」 は驚いて肩を跳ね上げ、彼の手を跳ね除けると電話中の碧の背後に周って彼との距離を取る。 「仁王くん、やめたまえ!」 柳生は彼を叱りつけると、に謝ったが、仁王と呼ばれた当の本人は悪びれもせず厭らしい笑みを浮かべている。 「いやー、でも。本当にこんなことってあるんだねえ」 「碧の言うことが本当なら、俺達これからどうなるんだろうな」 と濯の呟きが気になったが、はとにかく碧の電話の内容に耳を傾けた。碧が探している四人の正体がの予想通りならば、あちらの方が大変な事態になっているかもしれない。なんせ紫凪の中身は、幼児期からあまり成長できているとはいえないのだから。 back |