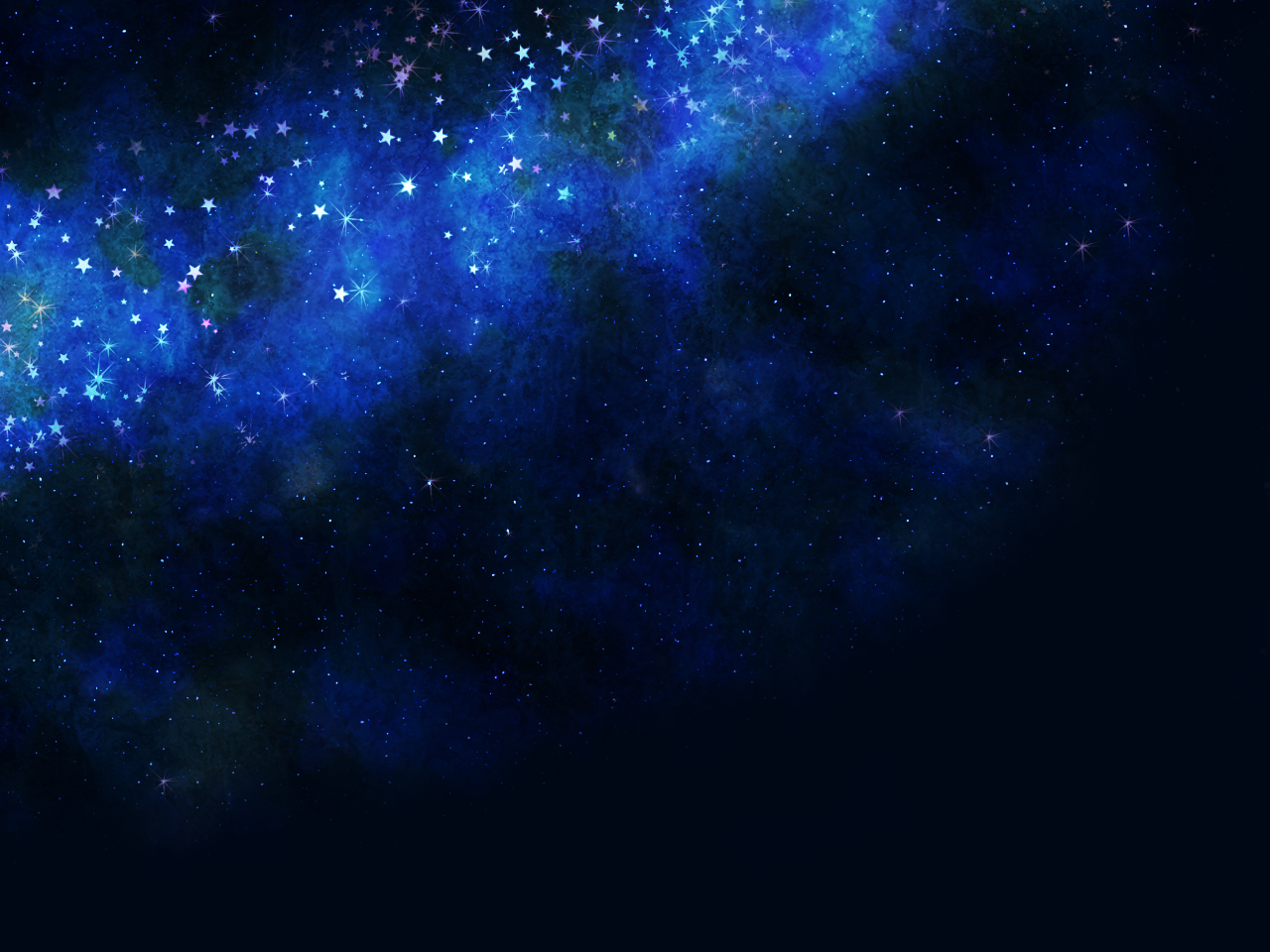|
「……あれ?」 最初に驚きの声を挙げたのは、紫凪と手を繋いで立つ双子の兄である紫凪純。幼い風貌の双子は、辺りを見回すと互いの顔を見合わせて首を傾げた。 重なる視線。同じ色の瞳を少しだけ曇らせて、双子は少し浅く息を吸う。 「ここ、どこ?」 二人の口からほぼ同時に漏れた言葉を聞き、彼らの背後で呆然としていた辻宮と癒月は我に返ってを庇うように引き寄せた。とにもかくにもの安全。それが彼らの決まりだった。 その腕の中で小さな手を伸ばしが指差した先に、三人は視線を集める。時代を感じさせつつも美しく整備された大きな門に掛けられた看板には四人がの目の前にそびえる門の先が学校であると物語っていた。 「ひょう、てい?」 氷帝学園中等部――聞き覚えの無い名前に、困惑する三人。それを余所に、は一人門越しに聞こえる声援に耳を傾けていた。女性の声の波はどれもが楽しそうで、は少しだけ安心したように息を吐く。 「ちゃん……」 「なんだ?」 門の向こうへ視線を投げたまま、はぼんやりと言葉を紡ぐ。少しずつ落ち着いて頭に浮かんだ言葉を、親友に伝えなくては。 「迷子、なの?」 「はあ? そんなわけ、ないだろ!」 そんなの言葉が気に触ったのか、は強く否定して腕を組んだ。中学二年にもなって迷子。は暫く渋い顔をしていたが、このままではのためにもならないことを悟ると深くため息を吐いての柔らかな手を取った。 「しゃーねェ、中で道聞くか」 それは提案ではなく、決定だった。宣言したは、の手をにぎったまま門を潜ってしまう。引き摺られるような形で、それでも抵抗せずにたちも彼女に続いた。このまま立ち往生というのでは、何にもならないと察したからだ。 「ちゃんたち、どこ行っちゃったんだろう……」 「ね、あそこ。人が居るから、あそこで道聞けばきっとなんとかなるよ?」 不安そうな声を漏らしたを励まそうとしたのか、純は人だかりを指差しての背中を撫でる。先ほどから響いていた歓声はこの人だかりから発せたれていたようで、たちと同世代に見える女子たちが集まっているようだった。彼女たちは一様に同じ制服を着ており、おそらくここの制服なのだろう。 「うわー……俺パス」 それまでおとなしくしていたが、艶やかな髪を揺らして後ずさりながら思わず愛らしい顔を歪める。少女にも劣らないその顔立ちは、彼の特徴でもあり彼の悩みでもあった。 の拒絶を聞き、もそれに同意して一歩下がる。 「アタシだってやだよ。あんな、興奮した女子軍団。学校なら、職員室とか事務室とかあるだろうし……」 「でも、こんな広い学校俺知らないよ……あそこの人だかりの先、ボールの音がするからテニスコートだと思う。きっと部活中なんだよ。そしたら顧問の人とかも居ると思うんだ」 「じゃあ、が行くね!」 ぴこんと片手を挙げ、見た目も口調の中身も幼い少女は満面の笑みを見せた。 「えっと、秋野瀬駅の場所が分かれば、大丈夫だよね?」 慌てて止めようとする純に見向きもせず、が軽やかに走り出す。なんといっても、もう中学二年生。現在地を聞くくらい、できるはずである。 「大丈夫かなー……」 「過保護すぎなんだよ、純は!」 「だって……可愛いから」 「シスコン」 純の過保護は今に始まったことではないのだが、それでもは呆れたように純を見る。の横では、やはりが心配そうな視線をの背中に投げていた。 一方そんな心配も露知らず、初めてのお使いに勢いよく挑戦中のは、人ごみに飛び込むとそのままその流れに流されていた。中学二年にしては小柄なの身長では、女生徒のひしめく中ではまともに動くことすらままならないのである。 想定外の事態に戸惑いを隠せないは、少しだけ泣きそうになりながら必死に前へと進もうともがく。それでも―― 「すみません……」 「キャー! 跡部様ぁ!」 「あのぅ、すみませ――」 「忍足くうん!」 「あの――」 「キャァァァァァアアァア!」 「ぐすん」 もう完全に泣いていた。ぼろぼろと大粒の涙を、アイスブルーの瞳から溢れさせ、それでもそれを懸命に拭いながら前にも後ろにも進めない現状をどうにかしようと身をよじる。しかし、すでにの足元は人ごみのなかでまともに地面についてはいなかった。 「ねえ、休憩時間よ!」 女子の群れの叫び声に、は首を傾げた。同時に互いに押し合い、人の波が激しく動き出す。は漂流するように、その波に流され、本人の意思に反してどこかへ流されていく。 驚きに涙も引っ込み、抵抗虚しくフェンスに身体を押し付けられたの瞳に、フェンス越しのテニスコートが映る。爽やかな水色と白を基調としたジャージを羽織った男子が、ざっと見ても百人は居る。が通っていた中学校も生徒は少なくなかったが、一つの部活がこれだけの人数を抱えているというのも珍しいものだ。 「心太になっちゃうぅ……」 ぎゅうぎゅうとフェンスに押し付けられ、は泣き言を漏らしてしまう。このまま押されていけばフェンスの網目を通りにゅるんとした心太になってしまうのではないか、の不安はその心の幼さ故に真面目なものだ。 情けない声は歓声に掻き消される。は、フェンスに張り付いた頬に痛みを感じ、再び瞳から大粒の涙がぼろりと溢れた。 「うわーん、痛いよぉ。純ーーちゃーん……助けてよぉ……」 時折腹部にぶつかる誰かの肘が、苦しい。その泣き言を、人ごみの外で純は聞きつけていたが、人の壁とも言えるこの人数の中からを助け出すことは彼には不可能だった。 「跡部様ぁぁぁぁ!」 一際大きい歓声が、の背後から上がる。涙で滲んだ視界に、誰かが立っていたがには検討もつかない。それ以上に、今はこのまま圧死してしまうか心太になってしまうかと、にはそちらの不安の方が大きかった。 強くなる圧迫感、迫る嘔吐感。その圧力は―― 「黙れ。雌猫共、散れ」 まっすぐに響いたその言葉で、消えた。 何事かとフェンスの向こうを横目で見るの視線に気づき、彼は一瞬に似たアイスブルーの瞳を見開いて明らかな動揺を見せたが、すぐに眉を寄せて訝しげな視線に変わる。 「大丈夫か?」 彼の横で、少し小柄な少年がに声をかけた。切りそろえられた髪がぱさりと揺れて、彼は子供をあやすようにしゃがんでを見上げている。 「あーあー、顔に痕付いてまうやん」 「……怪我は……ないですか?」 二人に続いて近づいてきた二人の男子もを心配するように見ている。体格の良い男子の問い掛けに、は「うん」と呟いた。 いつの間にか女子の軍団は一目散に散っており、フェンスに押し付けられていた頬をさすりつつはフラついた足取りながらも頭を下げた。 「うぅ……危ない所をどうもありがとうございましたっ」 (頬に菱形が……) の頬に、笑いをこらえる四人の男子に首を傾げながらは当初の目的を思い出したようで、ぴっと手を挙げて発言の意を示した。 「ところで道をお聞きしたいのですが! 秋野瀬駅はどっちにありますか!」 「なんや迷子なん?」 「秋野瀬……?」 「うん、秋野瀬駅! おっきくて、なんでもあるあの駅だよ!」 が身振り手振りを加えながら、再び声に出す。だが、返って来た答えは以外なものだった。 「聞いた事がねえな」 「え?」 は、ぽかんとして聞き返した。県内で最も多くの路線が交わる秋野瀬駅は、観光の拠点としても全国的に有名な駅である。知らない、というのはおかしすぎるだろう。仮にここが秋野瀬付近ではないにしても、この反応はの目から見てもおかしかった。 「え、で、でもさっきまで駅に向かって歩いてて……そしたら、ここ、知らない場所で……」 「お前、大丈夫か?」 は少し恐くなって、何も言わずに走り出した。何かがおかしい。この状況は、何かが。 (どうしよう……純、、ちゃん!) 三人の所まで走ると、はにぼすっと抱き着いた。はワケもわからずにの頭を撫でてと顔を見合わせる。 「、どうした?」 「! 何があった!」 「純、煩い」 はゆっくりと顔を挙げて、を見た。涙目でアイスブルーの瞳は煌めき、鼻先まで赤くなった顔で。それは、彼女を溺愛するには、あまりに刺激が強く――は思わずを容赦なく抱き締めた。 「愛くるしい奴め!」 「ぎゅぐっ」 「で、何があったんだ?」 から漏れたのは、よく分からない声。 小さな身体のどこかが、ボキボキと音を立てたがは気づかずにを抱きしめている。彼にとっては見慣れた光景なのか、は意識があるか分からないに問いかけた。 「アーン? こっちが聞きてぇなぁ」 ではない誰かの返事に、がバッと振り返る。そこには、怪訝そうな顔をした四人の男子が立っていた。彼らは先ほどを助けた四人だったが、それを知らないたちにとっては恩人でもなんでもない。は少し警戒しつつ、彼らを睨み付けた。 「ん、また随分可愛えコらが来よったなあ」 「俺のが可愛いのは世界の常識だから、何をいまさらって感じだけどね!」 「そっちの髪を降ろしてる子も……」 「俺は男だ!!!!!!!」 地雷を踏まれ、は大声で叫ぶ。 そんな会話もなんのその、泣きボクロが印象的な男子が、一歩前に出ると一つ溜息を吐いて口を開いた。 「そのガキが、変な事言うから気になって見に来たんだよ」 「つか、白目剥いてるぞ……」 「生きて……ますか……?」 「呼吸はしてるから、大丈夫だ」 に抱きしめられ、くてんとなっているに赤毛の少年と巨体の少年は更に不安そうな表情を見せる。大丈夫とが頷いて見せると、二人は少しだけ安心したようだった。 「で、何が言いたいんだよ、テメェらは」 「アーン? こっちの台詞だ。許可もなく氷帝の敷地で何をしている? まさか、本当に四人そろって迷子ということもないだろう?」 「だったらなんだっつーんだよ。あ? 迷子になっちゃいけねえ理由でもあんのかよ? 迷子迷子うるせえんだよ。なんだよお前、偉そうだな?」 はをに託すと、ずんずんと前に歩み出て、高圧的な男子と対峙する。彼のアイスブルーの瞳は、と同じ色でありながら、ずっと冷たくを見下ろした。 「俺様を知らない? ハッ、随分と無知な部外者だな……良いだろう。俺様の名前は――」 「景吾! その子たち捕まえて!」 男子の言葉を遮り、どこからともなく声が響く。耳の良い純は、その声が自分たちの背後からのものだと一人気づき振り返った。 「もしもし、仁王? 見つけた。居たよ、君たちが探している子たち」 深緑の髪が特徴的な、爽やかな生徒が景帯電話を片手に歩み寄ってきていた。彼は、携帯電話を手近に居たに無理やり手渡すと、申し訳なさそうに微笑んでみせた。 「使い終わったら景吾に渡しといて。僕、今日急いでて」 「は、え、景吾って、ていうかあんたも誰!」 「景吾携帯預かっといて! あと、父さんから何か聞かれても知らないって言っといて! 今日僕家に帰らないから!」 じゃ! そう言って慌しく去っていった彼に、呆然とするその場の面々であったが、彼が残していった携帯電話から響いた声に、たちは安堵することになる。 電話口の相手は、よく見知った人物だったのだ。 back |