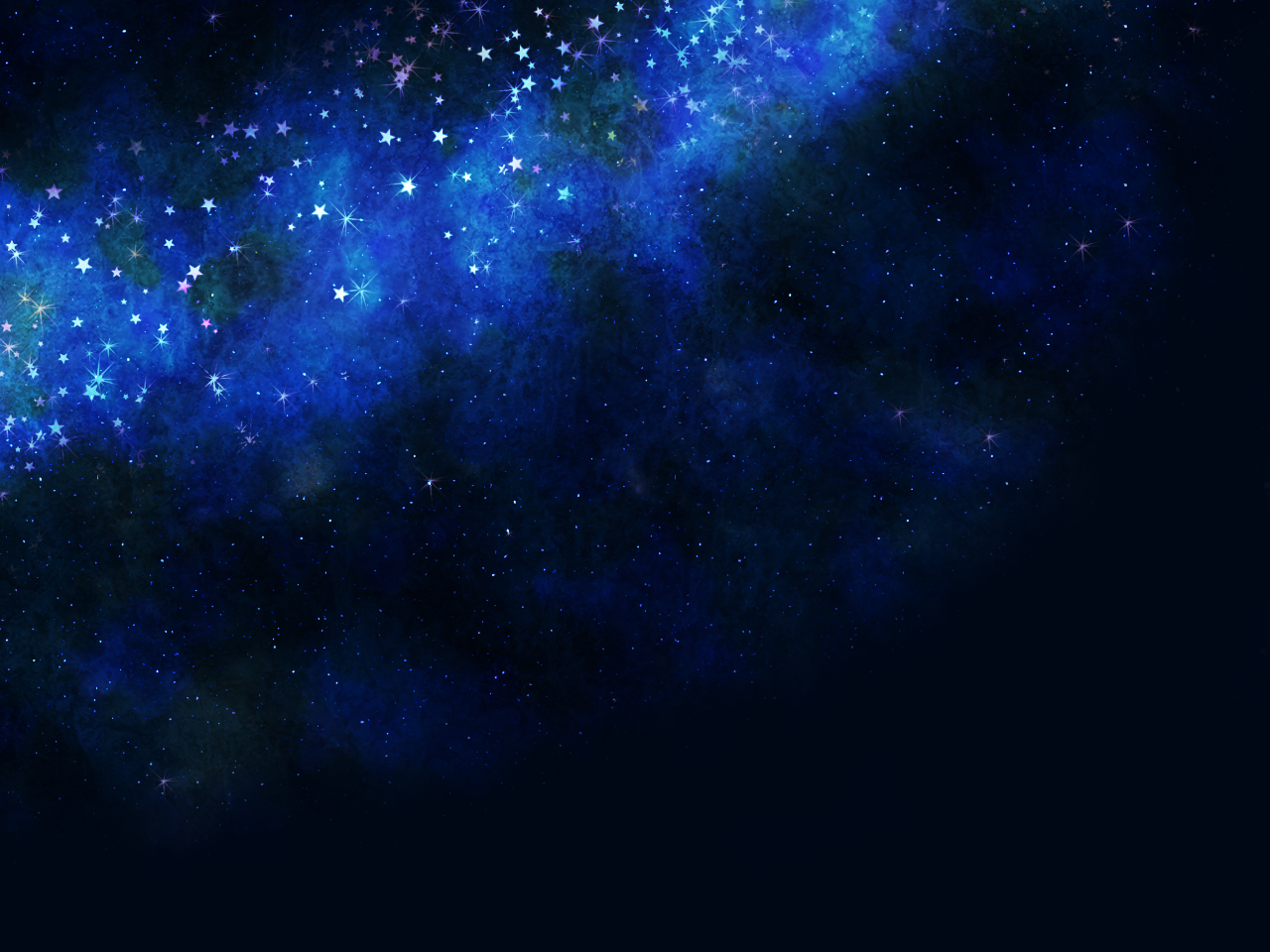|
地区予選を控えれば、練習にも力が入るというもの。 は慣れないマネジメント業務に追われながらも、彼らの熱意に負けないよう少しでも早く慣れようと懸命だった。 も珍しく真面目にやっているのだから、というのもある。彼女には少し失礼な話だが、よりも出来ないなんてことはとしても避けたいものである。 「〜、タオルは三つ折りにした方が、コンパクトに畳めるやも」 「えっ、そ、そっか」 「うんうん。でも、今の畳み方でも綺麗だった!」 一緒に暮らし始めて改めて気付いたのだが、やはりの方が家事は上手い。が極端にやってこなかったというのもあるのだが、にはそのことがすこし申し訳なくもあった。 「はさ」 「うん?」 「……なんでもないよ」 「何だよ! 言えよ! 気になるじゃんか!」 「――その、なんていうか」 一度飲み込んだ言葉を、はおずおずと引きずり出す。 「怒らない、よね」 その言葉にはきょとんとして、は彼女から少しだけ視線をずらす。 馬鹿にしたように聞こえたならどうしようか。そんな小さな焦りがあった。 「怒るよ」 「えっと」 「オイラだって怒る時は怒る。真田のこと馬鹿にされたり、物を盗まれたり、嫌なことされたら怒る」 「でも、は私に怒らないじゃない」 「なんでに怒らなきゃいけないのさ」 「だって私、何も役に立ててない。家事もできないし、テニスの知識もないし、それに今だって私に付き合ってが私の分まで多く働いてるでしょう?」 「何言ってんだこのきょにゅーはー!」 は突然がばりとに抱き着くと、の胸をがしりと掴んで騒ぎ出す。 は顔を真っ赤にしてじたじたと彼女から離れようとするが、何分彼女の方が力は強いのだ。 「!」 「改めて揉むとすごいねこれ! なにこれ! でっけー!」 「、いい加減にして!」 やっとのことで彼女を押しのけると、はにやりと笑って見せる。一体何なのかと問いかけるより先に、は満足そうなその顔で言葉を紡いだ。 「だって怒らないじゃん。多分それと同じだよ。あたしにとっての全部が、怒るようなことじゃない。むしろ大好きなとこだって、思ってる」 「……」 「何を思ってさっきみたいなこと言ったか、バカなあたしには分かんないけどさ。多分、は難しく考えすぎなんだよ。もっとオイラに分かる言葉に置き換えて説明して! そしたらきっと、それだけですっきりするよ!」 ね、との手を取ったの笑顔が眩しくて、は目を細めた。出会って長いわけではない彼女は、他の誰とも違う。腫物のように遠巻きに視線を送ることも、土足で踏み入ることもない。 清らかな素足を水面に浸すように、柔らかく、それでいて確信を抱くように。その触れ方が嬉しくて、愛しくて、出会ってよかったと思う。 「私は――悔しいのかもしれない」 「悔しい?」 「だって、の方が上手くできるなんて悔しい!」 「はははは、悔しいか」 「もう! 絶対家事も上手くなってみせるからね!」 「期待しておるぞ……」 「師匠感出さないで!」 そう冗談を言って笑い合うは、ふと視線をテニスコートに向けた。 「?」 もその違和感に気付いたのか、と同じように視線を向ける。 「……?」 最初は野良猫でも迷い込んだのかと思った。 だがその猫には耳が無く、尻尾もない。軽やかな足取りと、そこに居るのに誰の邪魔にもならず進むそれは、人の形をしていた。 「あの、人」 「こないだ、赤也を連れて行った人かな」 黒いショートボブに、猫目の少女。以前見かけた時は制服だったが、今は男子テニス部のジャージに下はスコート、片手にはラケットを抱えている。 彼女は迷うことなくテニスコートの端に居た仁王の前まで歩み寄ると、二・三言葉を交わして空いていたコートを指さした。 「なん――」 「〜!」 なんだろう。そう疑問を口にしきるよりも早く、二人は突然の声に勢いよく振り返った。そのまま崩れ落ちるに、は目を丸くする。 「ゆっきー!」 「ふふ、油断してたね」 崩れ落ちたの背に笑顔でのしかかった幸村の登場に、は小さくため息を吐いた。出会ってまだ数日だと言うのに彼の行動に慣れてきている自分に呆れているのだ。 「幸村部長……あの、に乗ると、彼女潰れちゃいますから……」 「しんでしまう」 「そっかあ、俺の愛情は重かったかな……」 「いえ、物理的に問題がありました」 よいしょとの上から降りると、彼はそのままの手を取って彼女を立ち上がらせた。その動きは自然で、まるでどこかの国の王子のようだ。 「練習中では?」 「うん。きみたち二人にお願いしたいことがあって、部長としての責務を果たしている途中です」 茶化すようにに敬語で返した幸村は、爽やかな笑顔のまま今度はに手を差し出す。 その手を取ると、見た目よりもずっと強い力ではぐいと引かれて同様に立ち上がった。 「もうすぐ大会だからね。スコアの取り方の説明とか、学校に提出する活動記録の書き方とか教えておこうと思って」 「あ、ありがとうございます」 「ええ……まじか……オイラそういうの苦手……」 「ふふ、そうだと思ったから。俺がしっかり教えてあげるからね」 「ちょうがんばって、すぐおぼえるぞお!」 そのまま二人は幸村に手を握られたまま、彼の後を歩き出す。 がちらりと振り返ると、コートでは先程の少女が男子部員と共に試合を始めていた。その姿が妙に気になっていると、幸村が繋ぐ手に微かに力を込める。 「部長、あの、あの人は――」 「うん? それより、どちらから教えようか。功乃さんは覚えが良さそうだから、教えるのが楽しみだよ」 「ありがとうございます、それより部長」 「あ、のことを名前で呼んでるのに親友のきみを功乃さんって呼ぶのもおかしいかな?」 「おかしくはないと思いますけど……」 そうこうしている内に、気付けば部室の中。 明らかにはぐらかされていることに気付きながら、はとうとう幸村への質問を諦めてしまった。 「さあ、しっかり覚えてもらうからね。俺が居るうちに、しっかりと」 「えあ……そっか、五月はもう……」 「?」 ぱたんと扉を閉じた幸村の言葉に、は俯いた。その顔を覗き込み、は首をかしげる。 「ゆっきー、入院するんだね」 「あれ……俺、に言ったかな……」 「ううん。でも、知ってるから」 はそのまま部室のパイプ椅子に腰かけると、首を横に振った。 「ええと、よく分からないけど……入院って言っても、検査入院だから。すぐに戻ってくるよ」 「ん……そうだね」 へら、と笑顔を見せる金髪の少女。はその背を二度優しく叩くと、の横に腰かけた。 「さあ、部長。最初はスコアボードから教えてください。もしが覚え損ねても、私が引き継いで教えますから」 「はは、頼もしいなあ」 に促され、幸村は二人の向かいに腰かける。 「さあ、始めようか」 はこの先この部に訪れる未来を知っている。そのことを、は知っている。 だけど彼女の知る物語と、今の自分たちが関わる人生は別だ。 だから、 「はい、よろしくお願いします、部長!」 二人はこの部のマネージャーとして、この部を支えていくのだ。 To be continued. back |