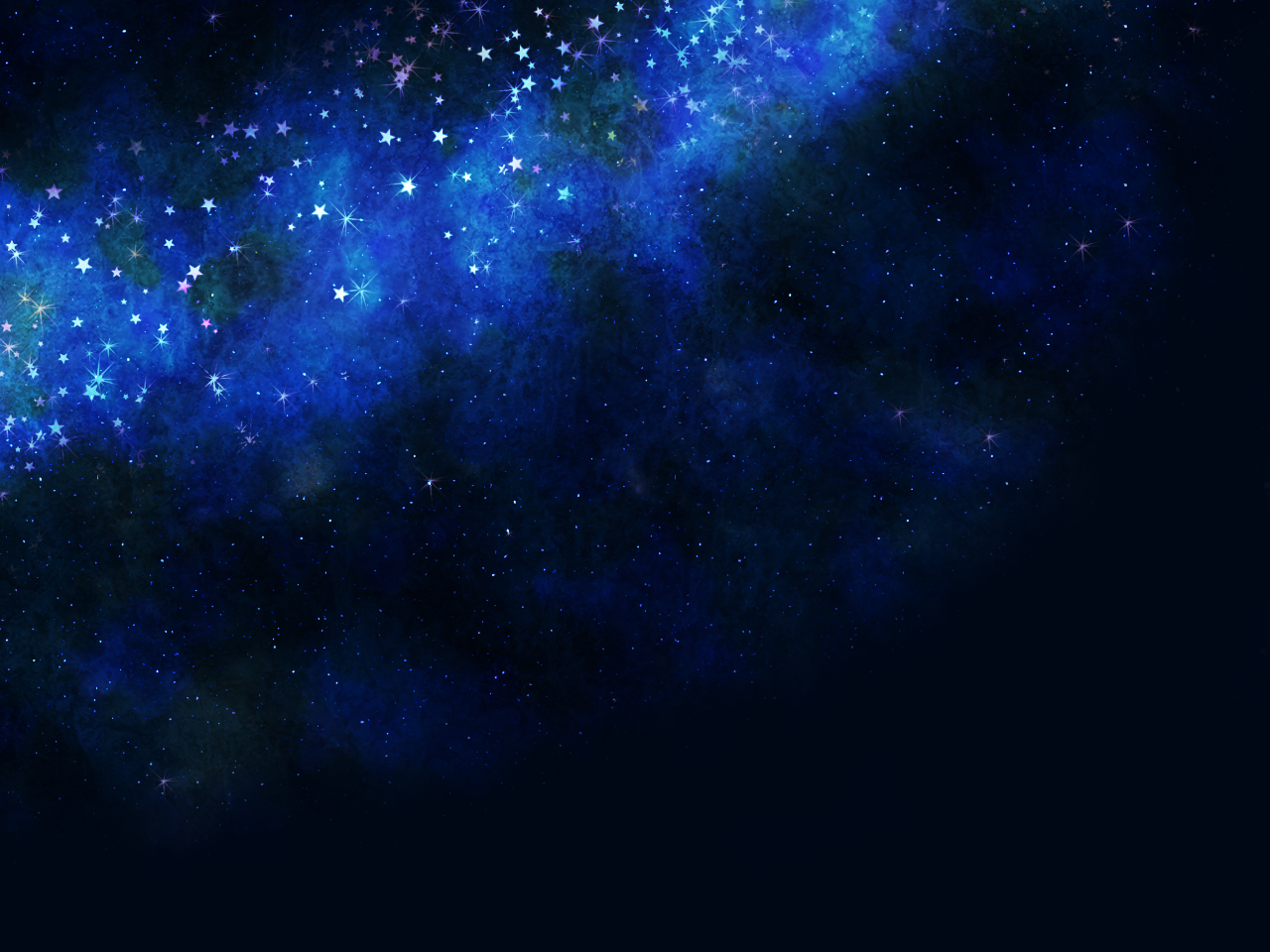|
人の波を進む足取りは軽やかで、いつか誰かに猫のようだと言われた。 それを言ったのは柳だっただろうか。 何分、すれ違う誰もが挨拶を交わすような人間ではないのだ。だから、一歩も足を止めずに、水城は部室棟へとたどり着いた。 扉の向こうに気配は一つ。部長だったら良いが、他ならば少し困る。何を話せば良いのか分からないのだ。 もう三年目にもなるこの部室。だが、にとって居心地の良い場所ではなかった。 それでも部を辞めないのは、がテニスを好きである以上に、部からの存在を求められているからだった。いや――存在、ではない。求められているのは、 「今日も勝たなきゃね」 勝利、だ。 は意を決し部室の扉を開くと、制服から着なれたテニスウェアへと着替えていく。そこに居た部員と言葉を交わすことはない。それは、望まれていないからだ。 さて、今日はどうしようか。 久しぶりに男子テニス部の練習に参加するのも良いかもしれない。監督に声を掛ければ、それも許されるだろう。 ショートボブの黒髪に指を通し、少しだけ整える。 ラケットを片手に、は部室を後にした。 back |