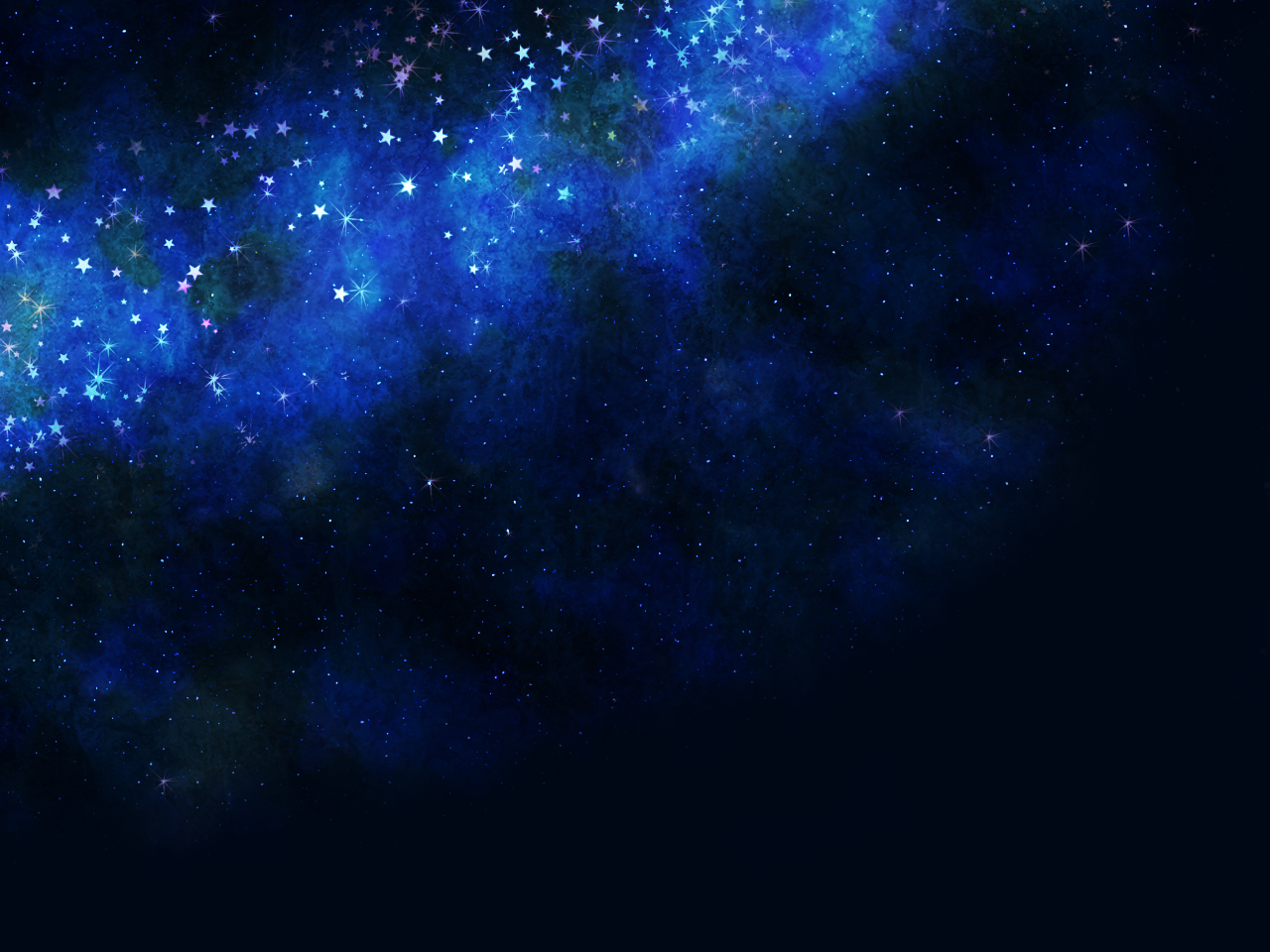|
「樺地くん、ドリンクのお届けでっす」 「ウス」 「どうぞー!」 「ありがとう……ございます……」 「えへへ」 二、三本のドリンクボトルを抱えて、はレギュラーたちと部室前を行き来する。 一度に沢山を持てないは、それでも持ち前の元気さで単純な作業をこなしていた。 難しいことはに任せればいい。は出来ることを、頑張るだけだ。それが、二人にとっては一番上手いやり方だった。 「ちゃん、運び終わったよ!」 「お疲れ。疲れてないか?」 「うん、大丈夫!」 「じゃあ、次はタオルを畳む作業だな。四角に折って、畳んでくれ」 「お任せ!」 の指示を受け、は部室へと駆けて行く。 三年部員たちからは既に随分人気なようで、走りながらは手を振る部員たちに元気に手を振りかえしていた。 「さて、と」 はそれまで作っていたドリンクを片付け、ボールの山になった籠を持ち上げる。 力仕事はの仕事だ。 「癒月、大丈夫か?」 「ん? あー、えっと、宍戸」 「先輩、だろ。まあいいや、あんま無理すんなよ。それ重いだろ、どっかにカート余ってなかったかな」 「いいよ、すぐそこまでだから」 「そうか。じゃあ、もう一個は俺が持って行ってやるよ」 「む……まあ、じゃあ、頼む」 自分が年上の男性に嫌悪感を抱かないのは、多分濯や碧のおかげだとは思う。 いや、父親たちを恨むのもおかしな話だ。だって、全ては自分が生まれてしまったから悪いのだから。 誰よりも健全に見えるの心に根付いた不健全な自己罰は、もう十数年物である。だから、がどれ程を許そうと、が何もなかったかのように接しようと、と楽しく言葉を交わそうと、それは簡単には揺るがない。 「もう夏だな、暑い」 「そんなうっとうしい髪してるからだろ」 「お前は随分さっぱりした髪型だもんな」 「宍戸も切ればいい。楽だぞ、短いと」 「んーでもなあ。願掛けっていうか、なんかもうここまできたら切るに切れないっていうか」 「そんなもんか」 「そんなもん。お前も、そのハイネック暑くないか? 日焼けとか、気にするんだなー」 「あー、まあ、そんなとこ」 他愛もない会話だ。 長くもなく短くもない、コート脇の用具倉庫までを繋ぐ言葉でしかない。 だからそんな会話は、すぐに終わる。 扉を開いて、籠を片付けてしまえば、仕事も終わりだ。 「ごくろーさん」 突然、の頭を宍戸はぐしゃりと乱雑に撫でると、にっと笑顔を見せた。 は少しきょとんとしたが、すぐに不機嫌そうな顔で彼を睨む。 「悪ィ、悪ィ。なんか男の後輩みたいで、つい、な!」 「なんだよそれ」 正直、頭を撫でられたのなんて初めてのことだ。 背の高いは、いつだって撫でる側だった。 「まあ、女子扱いされるのも変な感じだけどさ」 「へえ。なんか、お前絡みやすいな!」 「女子に慣れてない典型的な男子か、あんた」 「先輩だっつってんだろ! ていうか、別に女子に慣れなくたって、そういうのは跡部とかに任せとけばいいんだよ!」 「ははっ、否定しないんだ!」 がけらけらと笑えば、宍戸は苦い笑みを浮かべる。 他愛もない会話だ。だが、悪くない。 「だー、もう! 行くぞ! まだ練習時間だ!」 「はいはい。あー、おかしい。あんた面白いな」 「楽しんだようで何よりだよ!」 To be continued. back |