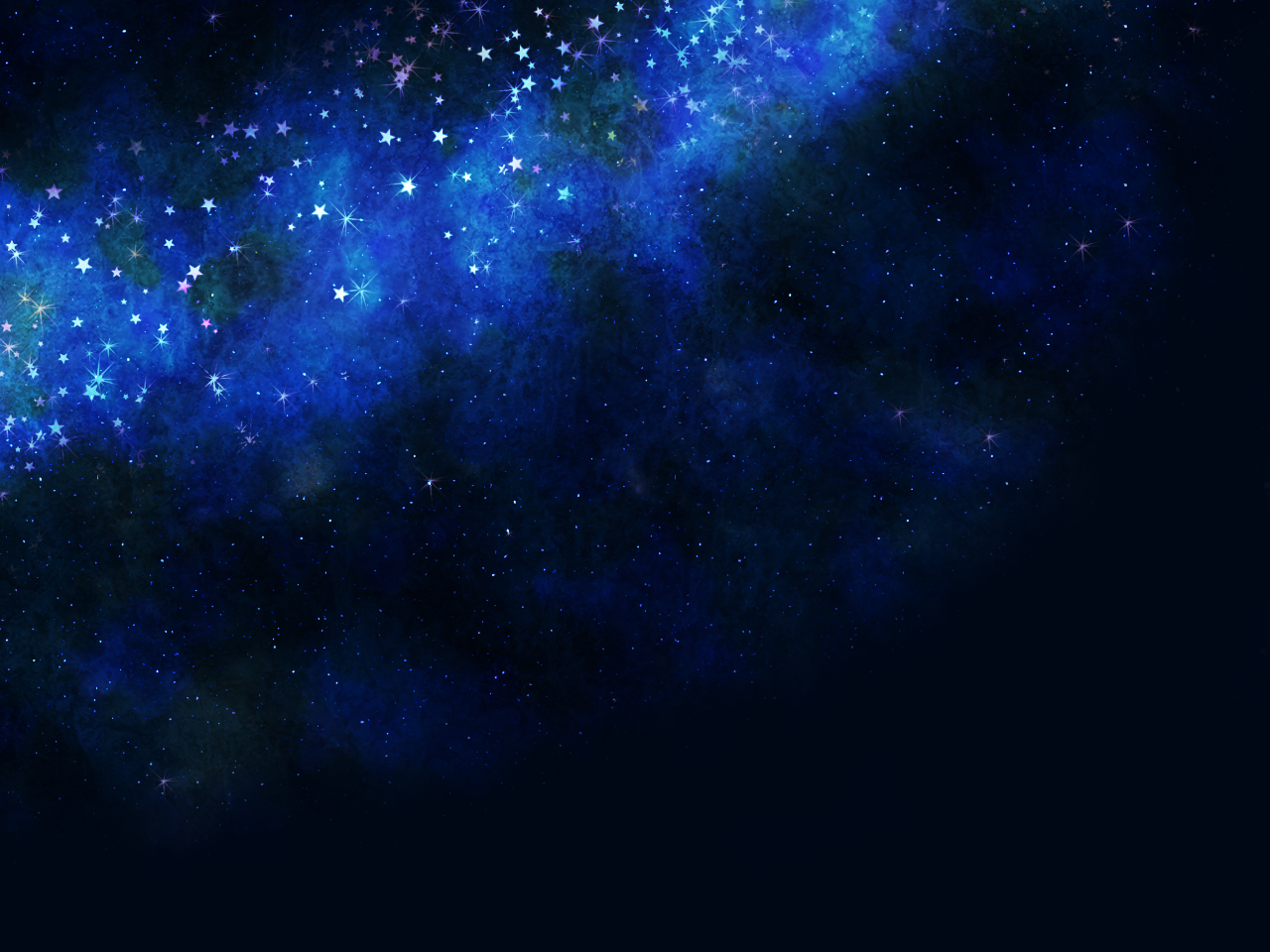|
テニス部入部と共に跡部から贈られた新品のテニス用具、新品のユニフォーム。 なれないそれらに囲まれながら、純とは顔を見合わせていた。 「うーん」 「なんていうか」 不安だ。 そう呟き、二人は苦笑を交わすとコートを見る。 テニスの経験はない。だが、ここは名門氷帝学園のテニス部である。自分たちのような未経験者など居ない。仮に居たとしても、新学期が始まって一ヶ月以上経った今ではまがりなりにも経験者だ。 「跡部部長はここで待ってろって言ったけど」 「その跡部さんがあっちこっち呼ばれまくってて、全然こっちに戻ってこれないんだもんな」 「はとマネージャー業に勤しんでるのに」 「は何だかんだで器用だからなあ」 「俺もマネージャーが良かったなあ。そしたら、とずっと一緒なのに!」 「いやいや、純だって運動神経良いんだから、それを腐らせるのはどうなんだよ」 「俺の運動神経はの為にあるの!」 「その台詞、もう何回も聞いたわ」 呆れながらにがコートをちらりと見ると、練習中の忍足が手を振る。 それを無視して視線を滑らせると、今度はようやく部員たちから解放されたらしい跡部が手を挙げた。 「純、、こっち来い!」 よく通る声に呼ばれ、二人は広いコートへと歩き出す。 跡部の前には、二人の選手が並んでいた。 「おまえら、テニスの経験は無いんだったな?」 「はい」 「そういうわけだ。鳳、日吉、基本的なことを教えてやれ」 跡部の視線の先。 並んでいた二人の選手が頷き、二人の視線が純とに移る。 一人は知っていた。鳳長太郎。先日、レギュラーとして紹介された部員の一人で、純たちと同じ二年生だ。 「よろしく」 人の良さそうな声色で、鳳は純たちに挨拶をする。 その隣。日吉と呼ばれた選手は、鳳と対照的に不機嫌そうな顔で口を開いた。 「日吉若、二年の準レギュラーだ」 「日吉、くん。うん、覚えた。よろしくね」 純が彼とは真逆ににっこりと笑うと、彼は苦い顔で溜息を吐く。 「なんで俺が、こんなこと……」 「教えることで見つかるものもあるだろう。それに、こいつらは俺様が見込んだ部員だからな。うかうかしていると、すぐに追い越されちまうぞ」 「その前に、俺があんたを追い越してやりますよ……下剋上だ」 「ふん、やってみろ」 生意気な口ぶりだが、跡部が咎めないところを見るに悪い人間ではないのだろう。 はぺこりと頭を下げると、彼にも挨拶をする。 「……跡部さん、こいつも部員ですか?」 「ああ」 「新しく入ったっていう、女子マネじゃなくて?」 「日吉。気持ちは分かるが、は男だ」 「!?」 自分の練習メニューに戻るという跡部を見送り、二人はさっそく純たちにテニスの基礎を教え始めた。簡単なルールから、ラケットの持ち方、コツ。 暫く続けていると、鳳はにこにこと笑顔で二人の肩を叩いた。 「二人共のみ込みが早いね。確かに跡部さんが言っていた通り、すぐに追い越されちゃうかも」 「ふふ、鳳の教え方が上手なだけだよ」 「日吉も、ありがとな。練習時間俺たちに使ってくれて」 「まあ、あの人の命令だからな……」 練習も一区切りというところで、はふとコートに目をやる。 自分も少し触れてみて、コートで機敏に動き回る選手たちがどれだけ凄いかを改めて実感したようだった。 不意に、ベンチに座っていた忍足と目が合う。彼はまたにこりと笑うと、に大きく手を振った。 「……」 相変わらず、呆れ顔だっただろう。 それでも、は仕方ないと言いたげに手を振り返す。 それだけで、忍足の笑顔はいっそう明るくなって思わずは吹き出してしまった。 「どうしたの、」 「っいや、別に……ふふっ、変な奴だなって思ってさ」 純に声を掛けられ、は忍足から視線を逸らす。 その顔は少女より甘く、純は少しだけ不安になる。 彼が愛らしいのは、知っていた。だから、怖かった。 彼が愛らしい故に苦労が多かったことを知っていた。だから、またそうなるのではないかと、怖かった。 「」 「うん?」 「俺の一番はだし、それは変わらない。でも、のことも俺は大事なんだ」 「なんだよ、突然」 「ううん、別に」 この可愛いイトコが傷つけば、きっとも悲しむ。 それに、多分この世界に来て一番救われたのはかもしれないと、純は思う。 「練習、再開しよっか」 知っているのは、純だけだった。 多分、純が知っていることをは気付いている。 でも、全部秘密。下手糞な知らないフリをする。 辻宮という商品のことなど、全て無かったことにしなくてはいけなかった。 back |