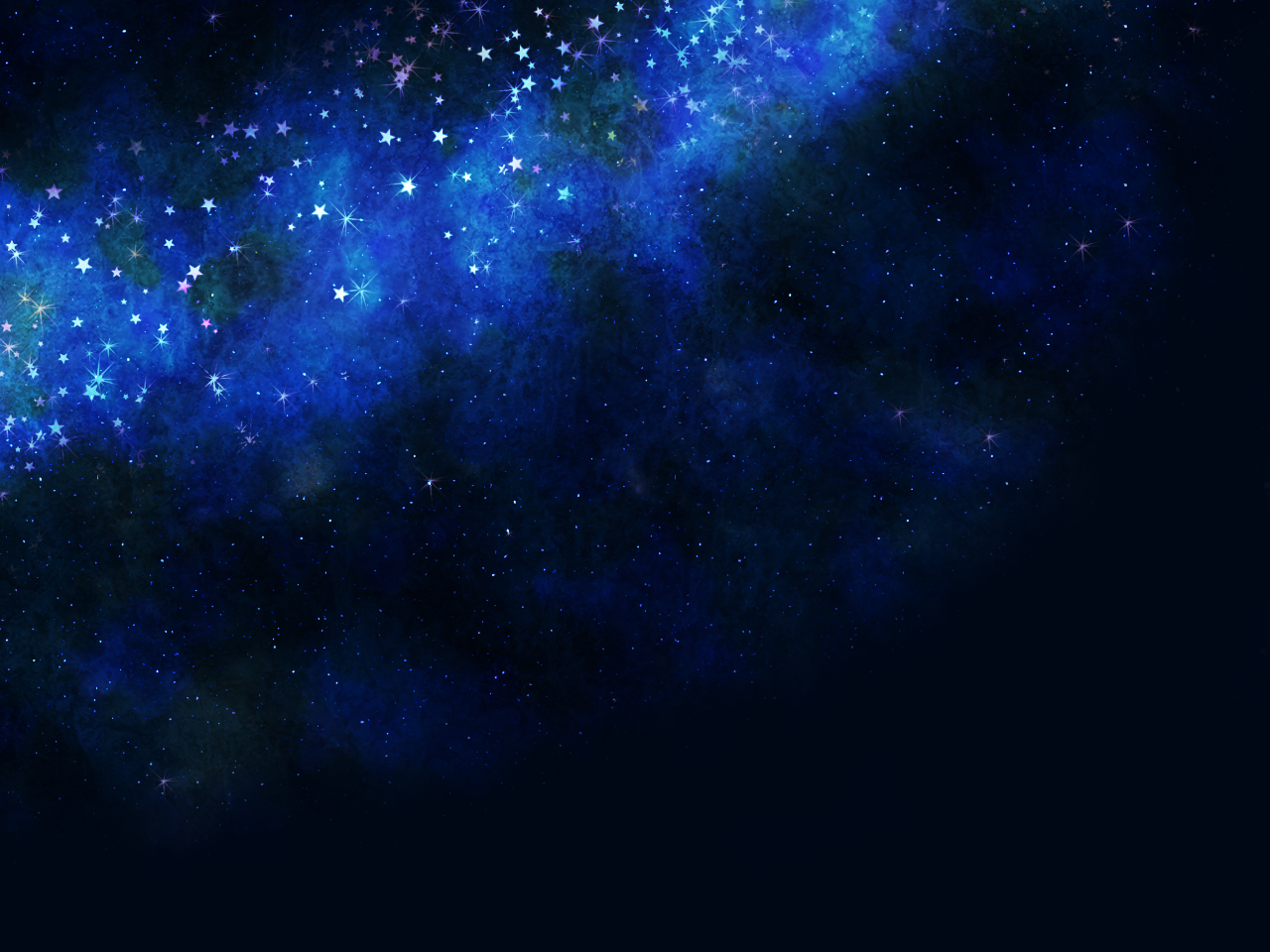|
「さーなーだー!」 酷く明るい声が、五月の立海大附属中学に響く。 黄色い声援を飛ばしているに、は少しの困惑と呆れを隠しきれずに溜息を吐く。 共に登校してきた筈の濯や碧は早々に彼女を見捨てて校舎へと入ってしまっており、奇行に走るを職員室へと引き摺って行く役目はに押し付けられていた。 「、危ないから降りて!」 「だーいじょーぶだって!」 呼びかけに応じず音を立ててが登っているのは、立派なテニスコートを取り囲む背の高いフェンスである。 正直言ってフェンスの向こうで練習中のテニス部員に迷惑だろうし、何よりフェンスを痛めるような行為を真面目なは許すわけにはいかなかった。 「……スカート……」 「平気だって、新しいパンツだから!」 「何か間違ってるよ!」 の目には丸見えの、隠さねばいけないの下着。それでもは何かを一心に見つめており、の呼びかけに応じる様子はない。 どうしたものかと戸惑うは、ふと背後に気配を感じて振り返る。 「これは、役得……?」 「……へ、へんた――」 「い、じゃないよ!」 言葉を遮り、の背後に突然立った少年は慌てつつもきっぱりと言い切った。 女性のように繊細な顔立ちの少年は、頭上のを多少気にしながら、どう注意したものかと困惑した表情を見せる。 は数歩下がると、じろりと彼を見つめた。 「あ、俺は幸村精市」 「はあ……」 の視線の意味に気付いたのだろう。 少年は幸村と名乗ると、清廉な笑顔を浮かべた。 は眼下の様子に気付いていないようで、相変わらず黄色い声援をあげるばかりである。 「さーなーだー!」 「、煩いよ! もう、本当に早く降りて!」 「あ、ごめ……おぉ!?」 本格的にに叱られ、振り向いたは目を丸くする。 フェンスを掴んでいた手はすっかり開いており、ぐらりと傾いた身体を立て直そうにも足場は最悪だった。 「!」 落ちる。確信的にそう感じたは反射的にぎゅうと目を瞑り、身を縮こませる。 その脳裏に、ふと、何かが浮かぶのを感じた。 (え……?) ――「駄目……ぶつかるっ」 ――「キャァァァアァァ!!!」 ――「っ……」 (何、今の……) 何か暖かな温もりと、切羽詰った誰かの叫び声。 浮かんだ情景に戸惑いつつ、のことを思い出したの瞳に飛び込んできたのはを受け止めた幸村の姿だった。 「ゆ、ゆゆゆ、ゆー!!!」 「!?」 壊れたラジオのように声を漏らすはがたがたと震えている。 きっと、高いところから落ちて驚いているのだろう。 「ゆっきー!」 「あ、俺の事知ってるんだ? なんだか嬉しいなあ……ふふ」 「スイマセンゴメンナサイハナシテクダサイ」 震えるがもがき、幸村の手を逃れようとする。 だが、何故か彼はそれを許さずに微笑んだままだ。 は生唾を飲み込み微かな緊張を抑え込むと、肩にジャージを掛けたままを抱きかかえる幸村の前でぺこりと頭を下げた。 「あの、が……その子が騒がしくしたことは謝ります。だから、彼女を放してあげてくれませんか」 「……!」 「え? ああ……」 とん、と。 の靴が地に着く音がしては顔を上げる。 「怒っているわけじゃないんだ。ただ、見慣れない子たちが居たから挨拶しようと思って……そしたら彼女が落ちてきて、キャッチしただけ。驚かせたみたいで、ごめんね」 「えっと」 スカートの中を覗いていたくだりが抜けていた気がしたが、それよりもに怪我がないことを感謝すべきなのだろう。 は礼を述べると、改めて自己紹介をした。 「私たち、今日からここに通うんです。だから、見慣れないのも無理がありません」 「今日から? 五月のこの時期に?」 「少し……複雑な事情がありまして……」 幸村はそれ以上詮索をせず、そうかと呟くとうんうんと頷いた。 それから気に入ったのかの頭をぐりぐりと撫でながら、優しげな瞳を二人に向ける。 「何か困ったことがあったら、いつでもテニス部においで。俺が力になってあげるから」 「無条件の助力、怪しい……!」 「こら、失礼なこと言わないの。えっと、幸村先輩、ありがとうございます。何かありましたら頼りにさせていただきます」 社交辞令だ。は簡素にお礼を言い、今度こそが勝手をしないように手を握る。 「道は分かるかい?」 「はい、校内地図をいただいていますから。先程は、本当にありがとうございました」 「、ひっぱらないで〜! ゆっきー! 真田によろしくね! また来るから!」 「、先輩だよ!」 ぶんぶんと手を振るを引きずり、は歩き出す。 職員室に、担当教師を待たせているのだ。 back |