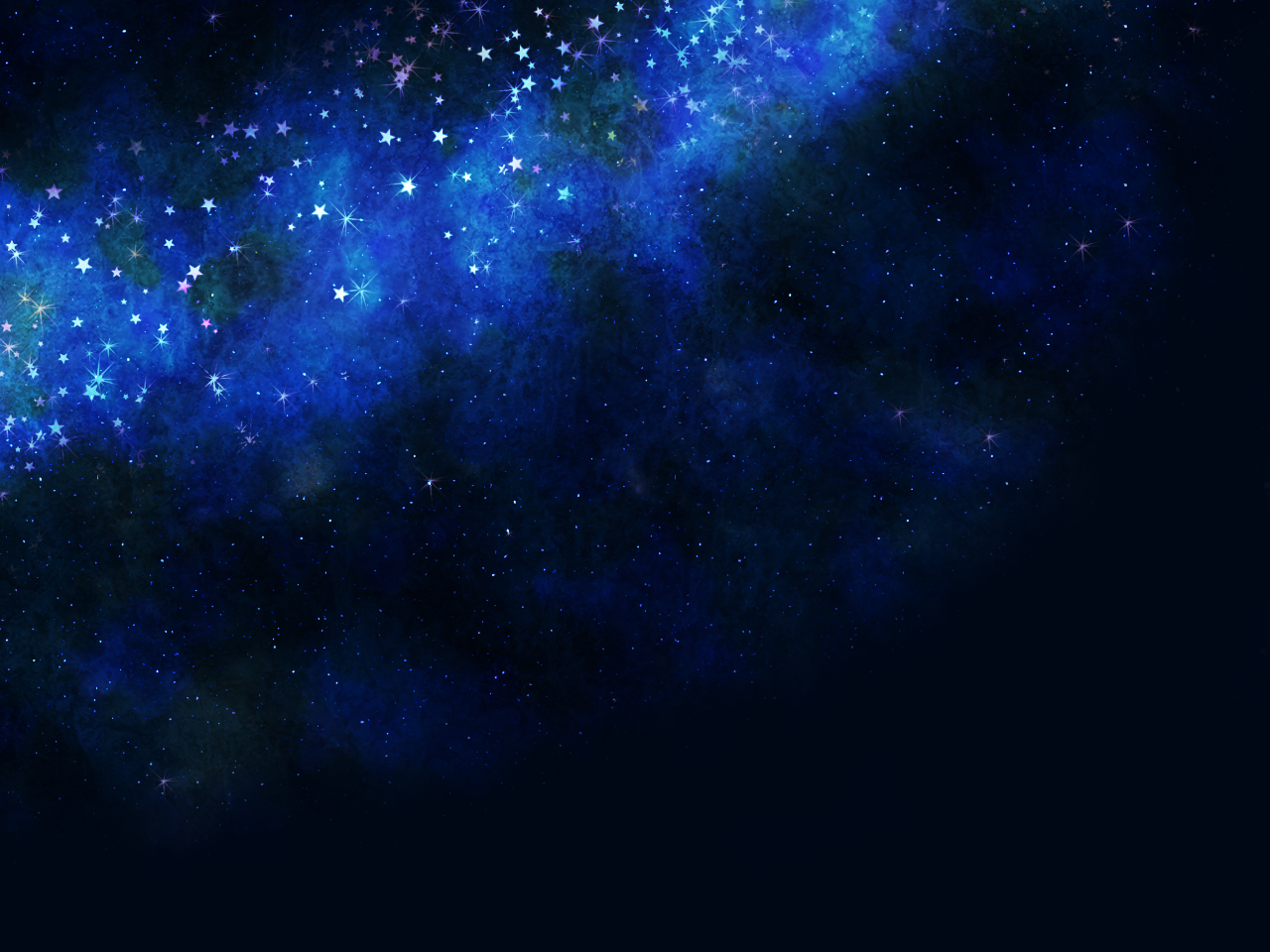|
その朝は、すさまじかった。状況も飲み込めないまま、跡部の用意した家に彼の家の使用人に案内され、学校の説明をされ、勿論一睡もできないまま朝を迎えたの苛立ちはすさまじく、空気を読んだは始終無言で朝食を用意するとさっさと着替えて家を出てしまっていた。 時間だけが悪戯に過ぎ、現状を説明するものが碧との確信だけであることからもこの世界が自分たちのそれとは異なることは仕方なしに理解した。何より、には――だけではなく、にも純にもにも、ここに居ない四人にも元の世界に戻りたいという気持ちは湧いてこなかった。あの場所は劣悪で、酷く残酷で。は制服から覗く喉元をそっと触り、鏡と向き合い呟く。 「やっぱり見える、な」 手を放したそこには、古い傷跡が服の下から走っていた。 彼女がワイシャツを脱げば、首の傷だけではない、切り傷、痣、火傷痕、それらが顔を覗かせた。これは彼女への不条理な罰であり、自分を産んですぐに家を出て行った母親が黒髪と共にに残した贈り物だった。 この傷を知っているのは、傷をつけた父と兄と、七人の友だけ。友人ですら、実際にこの傷を見たことがあるのはだけである。 春の陽気に暑苦しくもあるが、この傷を晒して生きるのは気が引けたのでタートルネックを一枚着るとその上からワイシャツに腕を通して朝食を片づけ、は誰も居ない家を出た。はとうに跡部が迎えに来ており、彼の車を純は走って追いかけて行った後だ。 同じ制服の学生がちらほらと歩く住宅街を、は足早に歩く。背の高い彼女に、氷帝の生徒たちは物珍しそうに視線を向けた。迷わないよう書いたメモを片手に、新しい制服にまごつきながらは傍に落ちていた空き缶を蹴り上げた。苛立ちを受け止めた空き缶は、青空の下で綺麗な弧を描き、 「ぁだっ」 通行人に盛大にヒットした。 「……やべっ」 缶を蹴り上げたままの姿勢で、は固まる。通行人はどうやら同じ学校の生徒らしく、すらりと綺麗な黒い長髪の右上を片手で抑えたままくるりと振り返った。 「てめえか、今の……」 明らかな苛立ちの声色に、既に苛立っていたは拳を振り上げかけたが、そこは理性が無理に抑える。缶を当ててしまったのは事実だ。 「悪かったな、ちょっと色々あってつい」 「ついじゃねえだろ!」 テニスラケットのケースを肩にかけた彼の怒りはもっともで、は返す言葉もなく苦い顔をした。煮え切れないの様子に、彼は更に苛立ったようでの胸倉を掴むと、強く睨みつけた。ちらりと横を見れば、既に学校の前までは来ていたようで、野次馬が達を囲んでざわついている。 その野次馬の中に、黒い蝶がひらりと舞った。 「ちゃんをいじめるなぁ!」 聞きなれた愛らしい声が、誰よりも低い位置から響く。思わず反応して声の主に向き直った長髪の彼は、声の主を認識すると同時に、倒れこんだ。 「ちゃん大丈夫だった?」 不安そうな色の大きな瞳が、をじっと覗く。の髪で、トレードマークの黒いリボンが揺れた。の後ろでは、を追って来たであろう跡部も呆然としている。 それまでの胸倉を掴んでいた少年は、の体当たりが見事に鳩尾に入りコンクリートの歩道に伸びていた。 「あ、ああ……」 跡部が野次馬を散らせるのも気にせず、はぎゅうとに抱きつく。 「よかったー」 愛らしい笑みを浮かべる彼女は、いつだってを助け出す。本人にその気がないのは分かっていたが、それでも愛おしく思わずにはいられない。 「おい、宍戸……?」 そんな中、跡部は倒れこんだ少年を恐る恐る覗きこんで彼の気絶を確認して溜息を吐いていた。ラケットケースを見る限り、彼が跡部と同じテニス部員だということは分かる。 「う? それ、景吾の知り合いなの?」 の疑問に、頷いて返した跡部をが名前で呼んでいることには眉を寄せた。しかし、今はあまり文句が言える状況ではないので宍戸と呼ばれた少年の顔を覗いてバツの悪い表情で跡部を見る。 「はあ。とりあえず運ぶぞ、手伝え」 back |