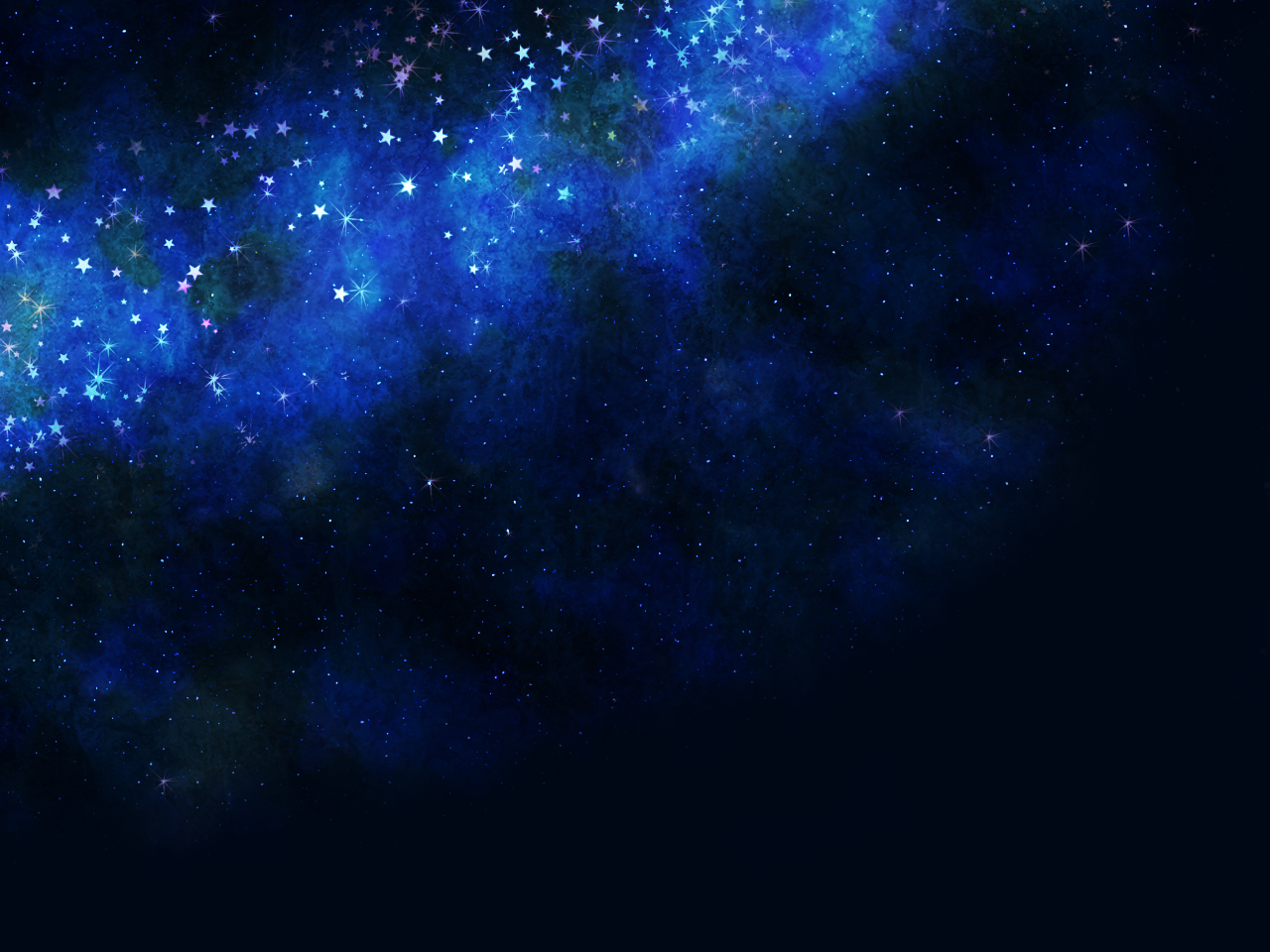白い恋人
(やっぱりこっちは寒いなぁ)
サク、
足の下で白が鳴る。
懐かしい、冷たい空気を吸い込んで吐き出せば、懐かしい声がした。
「士郎、」
「あ――」
名前を呼ぶより早く、喉が熱くなる。
手を広げれば、自分より遥かに背の高い彼が飛び込んできた。
「お帰り、士郎っ」
「ただいま、流くんっ」
白い世界で、二人は暫く互いを抱きしめあっていた。
寒いから、それもあるかもしれない。けれど、やはり一番はその温もりを確かめたくて。
「会いたかった、士郎」
「うん……」
軽くキスを一つ。
それから、雪の上を歩き出した。
「僕が居ない間、何かあった?」
「特に……あ、士郎を街興しのキャンペーンキャラクターにしようって市長が」
「えっ」
「流石に校長が断ったべ」
喜多海の家、喜多海の部屋。
慣れたその場所で、二人は他愛もない会話を笑顔で交わした。
「士郎、少し焼けた」
「沖縄まで行ったからね」
そう言って袖を捲くる吹雪。
「士郎……」
「ん?」
「こっち来て」
ふいに手招きされ、その通りに喜多海の膝の上へ。
吹雪は少し恥ずかしそうに顔を赤らめた。
「士郎の匂い」
「り、流くん?」
旅に出る前は隠されていた首筋に首を埋めた喜多海に、吹雪は少し体を引いた。
しかし、やはりその体格差からか吹雪の体は喜多海の腕にすっぽりとはまったままだ。
「士郎、会いたかった……」
「流くん……」
唇を寄せ合えば、体は自然と倒れ込む。
自らの体をまさぐる大きな手に、吹雪は抵抗をしなかった。
「流、くん……ふ、ぁ、りゅ……くん……」
「士郎……?」
「あの、ね」
ぐいと喜多海の頭を引き寄せて、吹雪は小さく囁いた。
喜多海は思わず顔を赤らめ、額にキスを落とす。
離れていた時間は長かったけれど、ずっと想っていた君を。眼前に居ることを確かめるように。
「だいすき」
そう言った吹雪のことを、喜多海も同じくらい愛しているから。
fin.