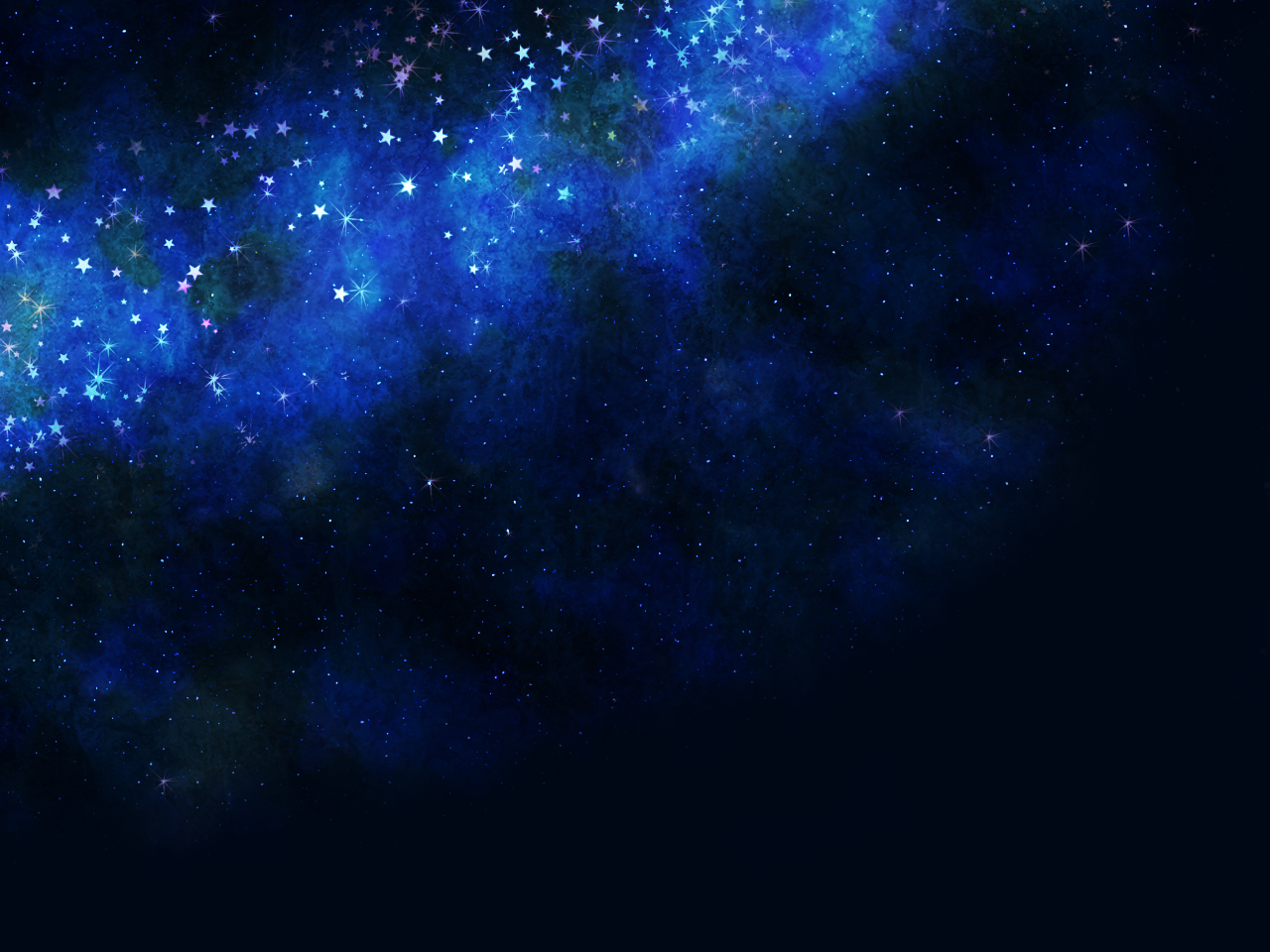赤
「I love you.」
赤は血液の色だって、父さんは言っていた。
「我愛イ尓」
だから、その流れる命一滴まで彼に捧げようと思った。
「あいしてる」
思っていた。
「あいして、た」
「ヒロト?」
沈みゆく夕日を見つめていると、背後から名前を呼ばれた。
咥内で繰り返していた言葉を聞かれたわけではないと思う。
しかし、不安を孕むような声色は多少なりとも俺をドキリとさせた。
「ほら、お茶。麦茶。これで良かったか?」
俺が振り返ったことで安心したのか、オレンジのヘアバンドが目立つ少年――円堂守は、俺にペットボトルを差し出した。
「うん、ありがとう」
オレンジ、というより既に赤く染まった街を望む鉄塔広場。そこに備え付けられた木組みの簡素なベンチに腰掛けたまま、俺はペットボトルに口を付けた。
守も空いた隣に腰掛け、街を眺める。
「守のは?」
その手に何も握られていないのを疑問に思い、問う。
鉄塔広場での練習を休憩にし、飲み物を買いに行くと言いだしたのは確かに彼だった筈なのに。
「ヒロトの一口貰うよ」
にっ、と悪戯な笑みに目線を逸らす。
守の笑顔が、太陽のようで身体が熱い。眼下に広がる街のように、赤く染まりそうになる。
「はい」
「ん、さんきゅ」
ペットボトルを手渡し、ちらりと彼を覗く。
何かを誰かと共有するのは、初めての経験だ。
かつて俺がジェネシスだった頃、すべてにおいて所有物は個々に渡されていた。部屋も、服も、食器も、風呂も、ペンも、何もかも。
「そんなに見て、取られるの嫌だったか?」
「え、や、そういうわけじゃないんだ! ただ、こういう経験が珍しくてね」
その視線が不快だったのか、守は俺にお茶を返そうとした。
それを否定し、俺は慌てて笑う。
ふぅん、と守は再びお茶を口にした。
「ヒロト、口開けて」
ペットボトルを口から離し、守が言った。
その言葉を理解しきれず、疑問を口にしようとして開いた微かな隙間にペットボトルが差し入れられる。
「ふ、く……」
多量のお茶が、喉の奥へと流れ込む。
咄嗟に飲み込もうともがくも、口角からはお茶が溢れては顔や服を濡らした。
「ん、んん……っがぁ、ごほっ、ぁぐっ……!!」
ペットボトルが抜かれるのと同時に、むせこんで恨めしげな瞳で守を見る。
彼はやり過ぎたとでも思っているのか、苦笑いを見せた。
濡れた服が気持ち悪い。
「まも、る……!?」
「知ってるか」
目尻の雫を拭いながら、守は唇を耳元へ近付けた。
「口つけた物を共有すると『間接キス』になるんだぜ?」
すっと身を引き、悪戯な笑み。
嗚呼、目が回りそうだ。
「な、にを……っ」
「それで、」
その笑みがぐっと近付いて、直後に唇に圧迫感。
思考が、ぐら、つ、く。
「これがキス」
分かった?
まるで子供にものを教える親のように、守は俺の頭を撫でた。
「ちょ、な、わ、もおぉ……」
「はは、」
俺が恥ずかしさのあまり俯くと、守は笑いながら体を傾けた。
「ここの夕焼け、綺麗だろ?」
「うん……」
「お前の、髪と同じ色」
顔をあげる。
燃えるような街が見えた。
綺麗な街が、一番すきな人が愛した街が、瞳に映る。
「守……」
「ん?」
嗚呼、幸せ。
そっと唇を押し当てて、彼の視界がこの色に染まればいいと思った。
fin.