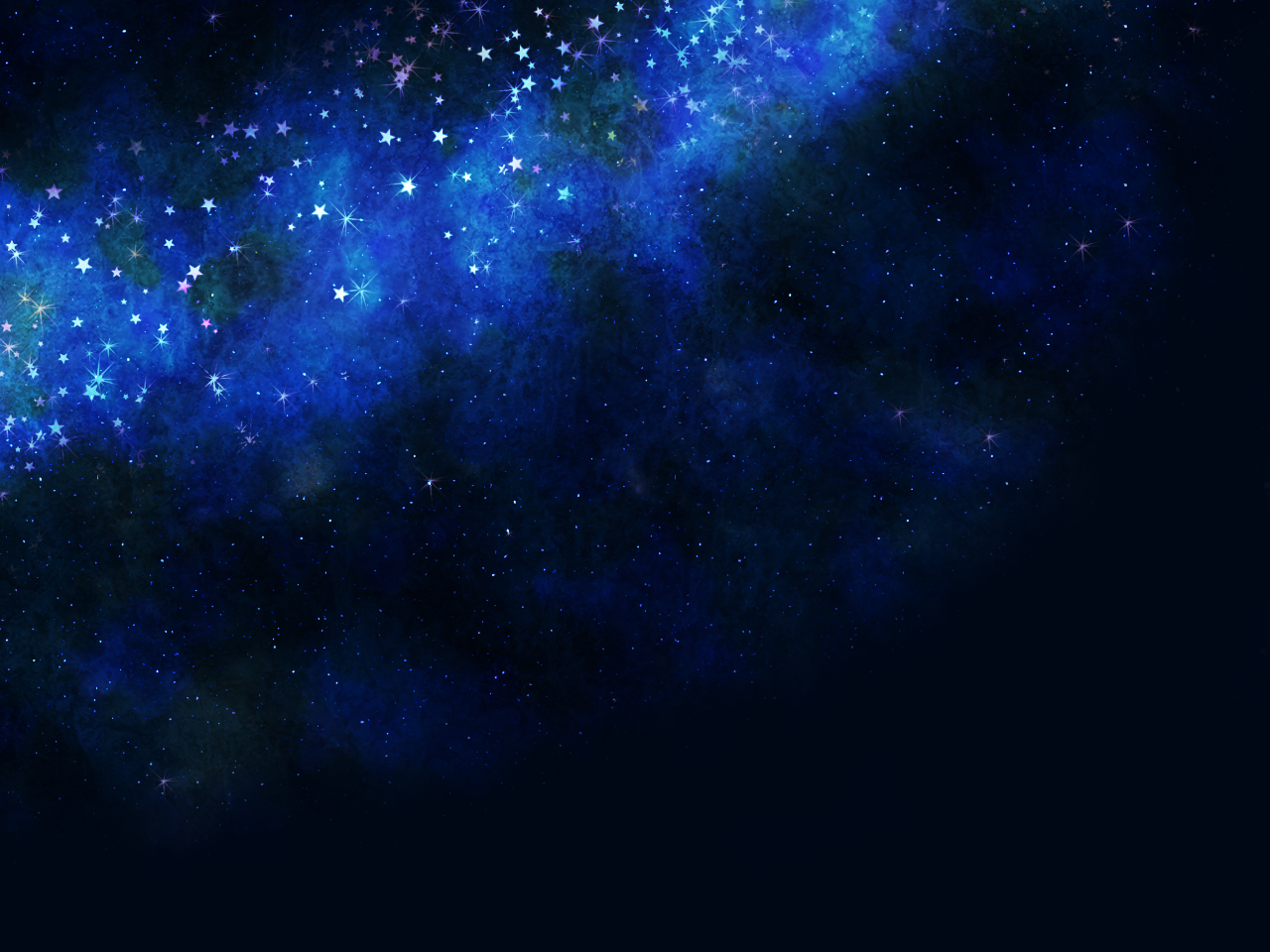Chicken or egg
もう十年も前の話。
母親を守ることができなくて、そんな俺を最上さんは似たような境遇の人が集まる場所に連れていってくれた。
そこには俺よりはるかに年上の人達が、似たような服装で寄り集まっていて、傍から見れば凄く怪しかった。それでも、その同じ色に染まった場所が、どうにも安心してしまったのだ。同じ悲しみの色を背負って、同じ恨みの色を背負って、同じ決意の色を背負って、深く繋がった共同体。いつか「ボーダー」と呼ばれるようになる、そんな組織だった。
最上さんは、組織の人達それぞれに俺を紹介して回った。名前を聴いて、顔を覚えて、彼らのほんの少し先の未来がちらりちらりと見えてくる。挨拶をするたび、その未来は少しずつ広がっていく。それは、自分一人に突き付けられていた絶望的な未来を塗り替えて、可沢山の可能性を生み出していく。
「おーい」
最上さんは、最後に一人の男の人に声をかけた。ロングコートのその人は最上さんの声に振り替えると、俺に気付いて少し困ったような顔をした。思えば、それは彼なりの驚いた顔だったのかもしれない。
前髪を分けた黒髪の、オニーサン。
「最上さん、その子は?」
その日何度目かの台詞を聴いて、俺は少し背筋を正す。第一印象は大事だから、笑顔も忘れずに。
「迅。迅悠一だ。今日から俺の弟子として、ここに出入りすることになる」
最上さんは何故か得意げに俺の背中を叩いた。それを合図に、俺は軽く頭を下げる。
「そうか。よろしく、迅」
彼は腰をかがめて、俺と目線を合わせて微笑んだ。
「私は忍田真史。私たちはきみを歓迎するよ」
黒い瞳に、自分が映っていた。瞳越しに自分自身と目が合い、ふと目の前の光景とは違う何かが見える。それが未来だと、俺は知っていた。
その未来を覗くと、そこには目の前の人物がやはり立っていた。同世代とは違い大人の変化はあまりに緩やかで、それがいつのことなのかはよく分からない。ただ、忍田真史と名乗った彼が、そこに立っていた。
彼は親しみやすい微笑みとは違い、はにかんでこちらを見ていた。少しだけ耳を赤くして、恐らく照れているのだろう。理由は分からない。未来から得られる情報というのは、存外万能ではないのだ。
「迅」
突然、名前を呼ばれた。
「すきだよ、迅。きみのことが」
――?
「……え?」
「どうした? 顔が赤いようだが……何か、私は変なことでも言ったかな」
そこには、戸惑った彼が居た。俺は、こっちが現在のことなのだと気付いて首を横に振った。
「ちがう、その、変なことは言ってない、です」
「最上さん、少し無理させたんじゃないですか? まだ小さいんですから、ほどほどにしてあげてくださいよ」
「わかってるわかってる」
それから、彼と最上さんが何か話しているのをぼんやりと聴いていた。聴いていたけれど、その内容なんて耳に一切入ってこなかった。
何だ、あの未来は。
そのことで頭がいっぱいになってしまい、頬と耳が酷く熱くなる。
すきだと言われた。その言葉は、子供ながらに間違えようがないくらい真っ直ぐだった。慌てて他の未来も模索するが、それでも、何度試してもあの光景にたどり着く。今日出会ったばかりのオニーサンが、俺をすきになる。俺は半分パニックになりながら、「いつかボーダーになる組織」の一日を過ごすことになった。
気付けば、近界民との戦いに最上さんが同行しなくてもそれなりにやれるようになっていた。人知れず人々の生活を守る暮らしは、それなりに気に入っていた。それでも一瞬でも忘れられないものが二つ、あった。
一つは後悔。俺が見えていながら助けることができなかった過去への、どうしようもない後悔。なんど謝罪を口にしても意味のないそれは、俺の全てを縛って、涙一つ許してくれない。
もう一つは、あの日からずっとそこにある未来だった。忍田さんと出会った日に見た未来は、未だに未来としてそこにある。何年も経ったのに、変化する素振りもなく真っ直ぐな気持ちを俺に向けていた。
いったいいつ、来るのだろう。
どれ程の近界民を倒して、どれ程の合数を打ち合っても、その未来は来ないのだ。
「すきだよ、迅」
その一言が、何度も何度も、未来で響く。だから、忍田さんと鉢合わせる度に俺はびくりと身を緊張させて、身構えてしまうのだ。そうする度に、そんな態度ばかり取ってはあの未来が変わってしまうのではないかと不安になる。不安になる度、未来は優しく微笑んでくる。
「すきだよ、迅」
どうしようもないくらい鼓動を加速させる言葉を、どうしてまだくれないのか。
「すきだよ、迅」
早く、早く――欲しい。
「すきだよ」
聞かせてよ、忍田さん。
「迅」
俺も、ちゃんと答えるから。
fin.